住宅価格の高騰を前提とした供給策が必要に 住宅を無駄なく流通にのせ、まずエッセンシャルワーカーへの供給を
日本大学経済学部 中川雅之 教授
日本大学経済学部の中川雅之教授は、実験・実証的手法を用いた都市住宅政策の経済分析を行っている。中川氏に、日本でアフォーダブル住宅を供給する方法を聞いた。
――「アフォーダブル住宅」の定義をどのように考えていますか
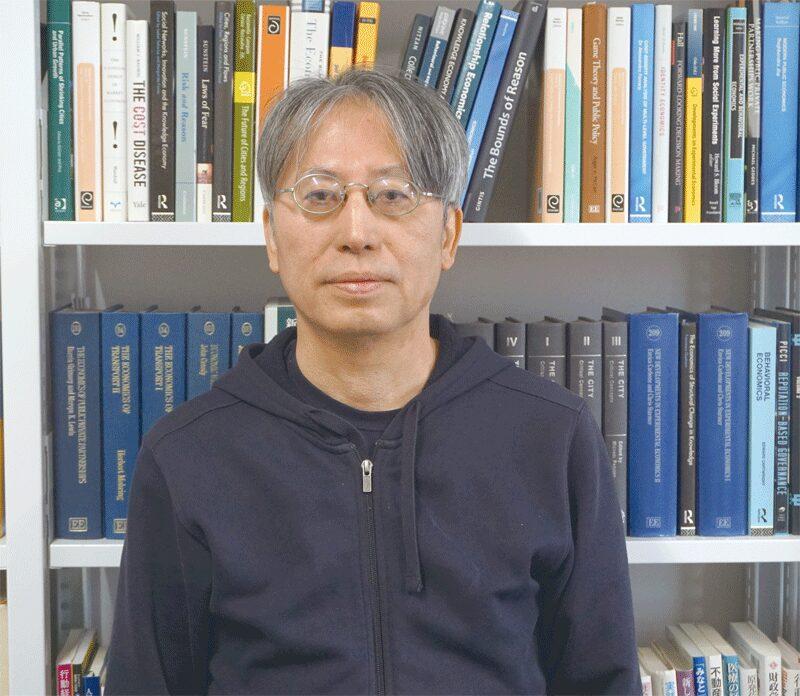
アフォーダブル住宅は世界でも幅を持った捉え方をされていますが、一般的には公営住宅やセーフティーネット住宅のような低所得者や、住宅へのアクセスが非常に厳しい人たちだけではなく、よりターゲットを広げたものを指すと考えています。
1990年代後半から、先進国では住宅価格の高騰が急速に進みました。その後、リーマンショックが起こったことで一時的には住宅価格が下がりましたが、2012年頃から再び上昇に転じます。さらにコロナ禍を経て、近年では再度住宅価格の高騰が深刻化しています。こうした中で、貧困層でない、一般層が購入・賃貸に関わらず都市に住むことが困難になってきているというのは、先進国の共通課題です。
そのため、低所得者や高齢者に絞らず、より対象を広げた住宅施策を行った方がいいのではないかという機運が高まり、各国でアフォーダブル住宅を支援する取り組みが行われてきました。
日本でもアフォーダブル住宅についての議論が様々なところで巻き起こっています。
日本で起こっている住宅価格の高騰には、主に2つの背景があります。
一つ目は、市場が資金で潤い、不動産が投資対象として注目を集めた点です。リーマンショック後、各国は金利を下げる金融緩和策を実施。さらに、市場に流通する通貨量(マネーサプライ)を増やすことで、景気を下支えしました。加えて、日本政府はコロナ禍の経済的な打撃を和らげるために、家計や企業に様々な補助金を支給しました。これによりマーケットがお金であふれ、なおかつ、金利が低く金融資産を持つメリットが減ったことで、社会全体で不動産を資産として保有しようとする動きが強まりました。
二つ目は、産業構造の変化に伴う大都市化です。産業構造が、製造業中心の労働集約型産業から、知識や情報をもとに価値を生み出す知識集約型産業へと移行したことで、知識や情報の共有がしやすい都市部に企業や人材が集まりやすくなりました。よく東京一極集中と言われますが、それだけでなく、政令指定などの都市には人口が集中してきています。
大都市は土地の供給が限られているため、人口の流入によって住宅価格は高騰します。そして、都市部の価格上昇が周辺地域にも波及し、全国的に住宅価格を押し上げる要因となっています。
――都市部に人口が集まるなか、中間層の住まいはどうなるのでしょうか
住宅価格の高騰を抑え込むことができるかといわれると、個人的には難しいと思っています。仮に抑えることができるとすれば、金融政策しかないと思います。
金融緩和策の後、インフレ懸念が強まったことから、欧米各国は金利を引き上げました。これにより、不動産価格はやや落ち着きを取り戻しました。
日本も金利の引き上げを目指してはいますが、現状は低いままのため、住宅価格の高騰が続いています。このように金融政策であれば不動産価格高騰に対する何らかの策は講じられると思います。
バブル期に地価が高騰した際には、規制によって価格高騰を抑えようとした動きもあります。監視区域制度といって、特定の区域(監視区域)で売買を行う場合は事前の届け出を義務付けることで、投機的な土地取引を抑え込もうとしました。しかし、根本的な解決には至らず、政府は、市場に直接的に関わって無理に抑え込もうとしても上手くいかないということを学んだと思います。
今、千代田区が投機的な取引を制限するため、5年間の転売規制などを行おうとしていますが、5年以内の転売が投機的なものかどうかは一概に判断できませんし、規制によって価格を抑えるというのは難しいと思っています。
一方で、価格そのもののコントロールが難しいのであれば、住宅価格が上がる、もしくは高い水準で推移することを前提とした政策が求められます。
例えば、東京都は民間と共同でファンドを立ち上げ、子育て世帯などへアフォーダブルな賃貸住宅を供給する事業を始めようとしています。
しかし、住宅は居住空間だけでなく資産という面も持つため、金融の動きと連動します。そうした価格変動に限りある税金を使った財政で対応しきれるとは思いません。「子育て世帯」のように、とても広い層に対して、財政的な支援を続ければ、最終的には財政破綻に陥ります。また、そのような支援策は、東京都のように税収入が潤沢でなければ行えないため、他の自治体での再現性は低いです。ターゲットを絞らないアフォーダブル住宅の供給は持続可能ではないと思います。
――アフォーダブル住宅を持続的に供給するためには、どのような方法がありますか
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
ジャパンホームシールド 2026年住宅市場予測オンラインセミナーを開催
2025.12.05
-
CLUE 住宅事業者向け“営業の工夫”セミナーを開催
2025.12.04
-
リフィード リフォーム人材戦略セミナーを開催
2025.11.25



