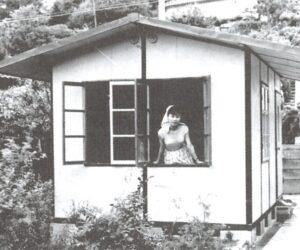省エネ化、木材利用、ストック活用、担い手不足‥‥多様化する課題に対応し住生活の質向上を
国土交通省 住宅局 住宅生産課長 前田 亮 氏
省エネ化の推進、木材利用、担い手対策など、住生活施策を取り巻く課題はますます多様化する傾向にある。
こうした状況下で国土交通省では、どのような施策を講じていこうとしているのか―。
住宅生産課の前田亮課長に話を聞いた。
――住宅・建築物の省エネ化という点では、適合義務化もスタートしましたが、今後の施策展開についてお聞かせ下さい。

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、2030年までに新築の住宅についてZEH水準とすることとしており、それまでに現行の省エネ基準を引き上げる予定としています。ちなみに2023年度の実績では、住宅全体で46.1%がZEH基準の省エネ性能を備えているという状況です。
また、2050年までにストック平均でZEH水準を達成することを目標としています。この目標を達成するためには、既存ストックの省エネ改修を進めると同時に、新築段階で現行のZEH水準を大きく上回る住宅を増やしていく必要があります。
子育てグリーン住宅支援事業では、ZEH水準を上回る性能を備えたGX志向型住宅に対する補助を創設しました。想定以上にご活用いただいた結果、7月22日に予算額の上限に達しました。また、経済産業省においては、現行のZEH基準を強化したGX ZEHを新たに導入することを予定しています。
今後も関連省庁と連携し、支援策を講じながらZEH水準を上回る性能を備えた住宅の普及を後押しする必要があると考えています。
――住宅・建築物を販売・賃貸する事業者に対して、省エネ性能を表示する努力義務も課せられました。
共通の省エネ性能ラベルを用いて、販売時の広告などに省エネ性能を掲載する取り組みだけでなく、大手の不動産ポータルサイトにおける省エネラベルの掲載も進んでいます。2025年4月時点でのラベル掲載数は、8万9133件に達しています。
このラベルによって、省エネ性能を見える化していくことで、消費者が住宅を選択する際に、省エネ性能を判断材料のひとつにするような市場環境が創造されていくことを期待しています。
――2026年度に向けた概算要求では、賃貸住宅のZEH化に向けた新規事業を盛り込んでいましたが。
戸建住宅などと比べると、賃貸住宅のZEH化は遅れていると言わざるを得ません。賃貸住宅の場合、ZEH化するとコストがかかるが、賃料水準に反映しにくいため、なかなかZEH化が進まないという現状があります。
こうした状況を考慮して、2026年度の概算要求においては、オーナーの方々にもZEHを選択肢のひとつとして認識してもらえるような支援策を計上しています。
――建築物のライフサイクルカーボンの削減も重要な課題になっています。
世界のCO2排出量のうち、建築物関係が約4割を占めていますが、このうち四分の一にあたる約1割は建築物に使用する建材の製造などに伴う排出であると言われています。現在の建築物の省エネ化に向けた対策は、主にはオペレーショナルカーボンと呼ばれる使用時のエネルギー消費量を削減しようというものですが、今後は建設資材・設備の製造、建築物の施工・解体を含めたライフサイクルカーボンの削減が求められます。EUなどでは、既にライフサイクルカーボンに関する規制なども行われています。
国土交通省では、「建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会」などを中心として、建築物のLCA(建築物のライフサイクル全体におけるCO2を含む環境負荷を算定・評価すること)の実施を促す制度の構築に向けて検討を進めているところです。
制度化に当たっては、まずは大規模な非住宅の建築物を中心に取り組むことが議論されています。住宅分野におけるライフサイクルカーボンの削減については、コストを負担する施主や居住者のメリットが見え難いといった課題があります。一方、住宅についてもLCA実施の一定のニーズはあるため、実施したい人ができるような枠組みが議論されています。また、官民で構成するゼロカーボンビル推進会議においては、戸建て住宅向けの算定ツールの整備が進められているところです。
空き家になる前に既存住宅市場で流通される仕組みづくりを
――26年度に向けた概算要求を見ていくと、ストック分野での事業が目立ちます。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説
2026.01.22
-
CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術
2026.01.15
-
CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催
2026.01.15