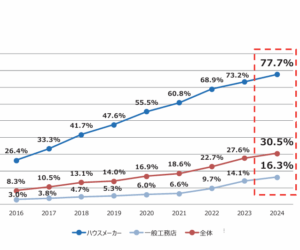平時の成功が有事に効く
立教大学と(一社)日本モバイル建築協会は、「モバイル建築研究プロジェクト」をスタートした。将来、南海トラフ地震が発生すれば、84万戸の応急仮設建設が必要になると予測されているが、同協会の長坂俊成代表理事は、「現行の法制度、仕組みの中で、供給責任を果たすことは難しい」と指摘する。このプロジェクトは、平時から地域の中小製材所、工務店などが中心となり、モバイル建築を地域分散型で生産供給できる新しいサプライチェーンを構築することで、南海トラフ地震などの有事にも備え、84万戸の応急仮設住宅の供給責任を果たしていこうとする壮大なものだ。
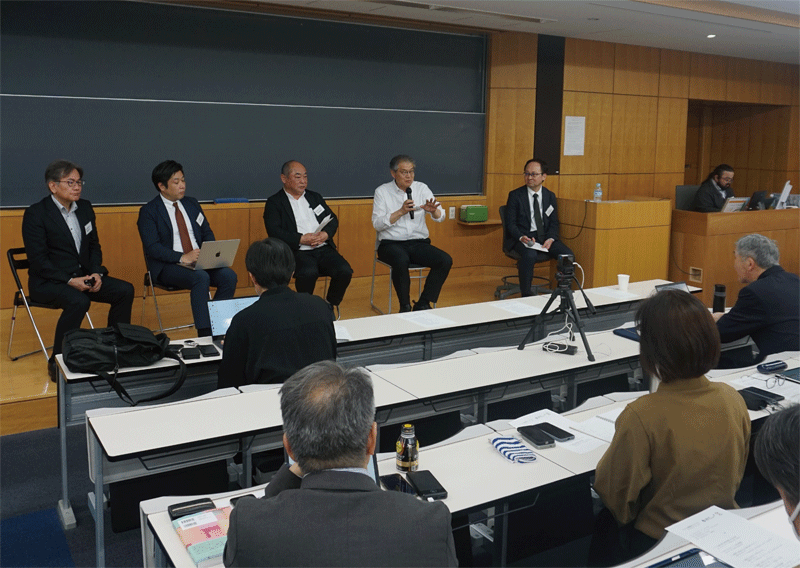
同プロジェクトにメンバーの一人として参加するウッドステーションの塩地博文会長は、「南海トラフ地震が発生すれば敗戦に近い状態になる。その国難に我々を助けてくれるのは山ではないか。住宅産業に限らず、工業生産の立地は沿海部にあり、南海トラフ地震が発生すれば、大きな被害を受け生産がストップするリスクは高い。復興資材として、また、生産拠点として山が持つポテンシャルは大きい」と話す。
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術
2026.01.15
-
CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催
2026.01.15
-
フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説
2026.01.13