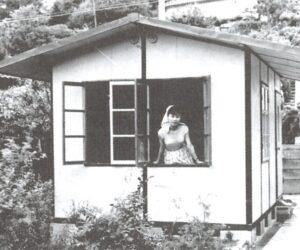用途や使い方を明示して発注しよう 無垢材特有の事情を把握したい
川下に近い賃挽き製材
先日、ある木工団地(木材業者が軒を連ねている工業団地)の製材加工業者を訪ね、木材の加工や流通について聞くうちに、「材木屋」と呼ばれる立場の仕事が以前とはかなり様変わりし、結果的に木材を扱うプロとしての技量が低下しているという話になった。

その業者は製材機を持ち、丸太からの製材も行っているものの、団地自体が消費地に近いこともあって、建築現場ですぐに使うような材料をつくる仕事が多く舞い込む。具体的には、丸太を大きく挽き割ったブロック状の原板を指定された寸法の造作材に挽き割ったり、階段板や框を挽いたりと、見えがかりの仕上げ材をつくる仕事を頼まれることが多い。
材料は先方からの持ち込みで、「これをこういうふうに挽いてくれ」と頼まれて製材する賃挽きの仕事になる。仕事の依頼先は、工務店や設計事務所といった作り手もあるが、同業の材木店が多数を占めるという。
サイズや品質だけの注文では困る
フローリングや羽目板、さらには各種の枠材や廻り縁・巾木といった見切り材といった仕上げ材にカタログ製品の「建材」が多用されるようになって久しい。メーカーと品番を指定すれば間違いのないものが届き、多少の長さ調整などは必要でも、鉋で仕上げたり、面取りしたりせずにすぐ使えるから扱いも楽だ。当然、材木店でもこうした建材類を扱う機会が多くなっていて、どこの店にもメーカーのカタログが常備されている。
だが、こうした建材ばかりを扱っていると、いろいろと面倒なことが起こりがちな無垢の材料に関するスキルがどうしても低下してしまう。今回訪ねた製材加工業者はそのことを盛んに嘆くのである。
オーダーメードで無垢材を仕立てるその業者のもとには、カタログ建材ではなく、無垢の材料にこだわる向きからの仕事が入ってくる。何度か前の本欄で「特別なサイズがまかり通っていることが流通の非効率につながっている」と書いたが、無垢の仕上げにこだわるとなると、サイズも通り一遍のものではなくなるケースが多く、その業者が注文される材料のサイズは実にさまざまだという。
賃挽き製材という業態はそもそも顧客のニーズに細やかに対応するのが本分であるし、その分、加工賃はしっかりともらうわけだから、サイズが多様だというのは特に問題はない。
困るのは、注文された材料が最終的に何に使われるかがはっきりしない場合だ。どのように使われるのかも把握できなければ、やはり困る。
材木屋のスキルが低下している
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
旭ファイバーグラス・旭化成建材 G3プロジェクト4棟目の実例報告会をウェビナーで開催
2026.01.27
-
日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説
2026.01.22
-
CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術
2026.01.15