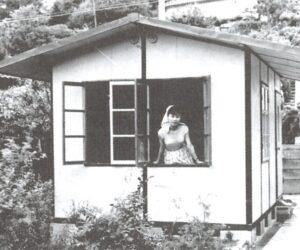お正月の価値/まだ、まだ息づく日本人のDNA
お正月の価値
子どもの頃、正月は大きな楽しみだった。何しろお年玉をもらえるのが嬉しい。親はもとより年始挨拶に来たお客様や近所の人までがお年玉をくれた。近所の駄菓子屋へ走った。駄菓子屋は子どもたちの天国。近くのいたずらっ子が皆な集まってアメや玩具を買ったり、くじ引きをしたり、他のほとんどの店が正月は休みになるのに駄菓子屋だけは開いていた。子どものお年玉を狙ってだ。だが今は、そんな子どもたちが集まる駄菓子屋はほとんど姿を消したし、子どもたちにお年玉の使い道を聞くと「貯金します!」の言葉が返ってくる。子どもからの経済も今や回らない。
古典落語の世界ではお正月の風物の前口上がよくあった。新年早々に〈えーお宝、お宝ぁ、お宝〉の売り声が町に響いたという。木版刷りの絵で、宝物を満載した龍頭の帆かけ船に乗った七福神が描かれている。右側には「なかきよのとおのねぶりのみなめざめなみのりぶねのおとのよきかな」(長き世の遠の眠りのみな目覚め波乗り船の音のよきかな)の和歌が。ご推察のとおり、この歌は回文。上から読んでも下から読んでも同じのお目出たい歌。まさに宝船、七福神、回文のお目出たの三つぞろいで、この絵を元旦か二日の夜に枕の下に敷いて寝ると、良い初夢を見られるという年の始めの縁起かつぎだ。
正月には子ども相手の“宝引き”の売り声も。子どもたちは小銭を握りしめ、今年1年の運だめしをしたという。束ねられた十数本の細い糸の先きに印しがついていて引き当てるとアメやおもちゃの景品がもらえた。これも運だめしだ。また、春を告げる“福寿草”売りも町を流していたそうで、あれや、これやで江戸の頃の正月の町は今と違ってさぞかし賑やかだったに違いない。そう言えば、駄菓子屋もさることながら子どもたちは、外に飛び出し羽根つきやタコ上げにも夢中になった。やがてこれに大人も参入し、どちらが主役か分からない熱中ぶりでもあった。だが今はこんな風景も少ない。道路でクルマにでもぶつかったらどうする、というわけだ。正月の影は薄くなる。
考えてみると、正月のほんの一週間前はクリスマスだ。この日は会社から父親も早く帰ってきてジングルベルを歌いながら家族で大きなケーキを切る。翌朝、起きればサンタクロースからの欲しかったゲームなどが枕元にある。賢い子どもたちはサンタはお父さん、お母さんだと分かっていながら素直にサンタさんのプレゼントが嬉しく、楽しい。いまや、完全に正月よりクリスマスに軍配が上がる。「もういくつ寝るとお正月~」なんていう唱歌も時代離れで今やお正月を迎えるドキドキ、ワクワク感はすっかり影をひそめている。“お正月の値打ち”が下がったということだろうか。
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
リフィード 社員リレーによるオンラインセミナー「リフィードのこぼれ話」いよいよ後半へ
2026.02.16
-
硝子繊維協会 住宅の設計・施工者に向けた特別セミナーを開催
2026.02.16
-
(一社)リビングアメニティ協会 「健康×省エネ×快適をつくる断熱リフォーム」を解説するセミナー
2026.02.09