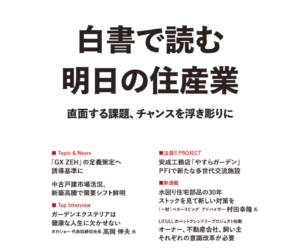憧れの“隠居宣言”/隠居家をつくる
憧れの“隠居宣言”
定例の記者OBの集まり。一人が高らかに宣言した。「こんど隠居することにした。ついては隠居家をつくろうと思う。知恵を貸せ」。これはまた、隠居とは古めかしい言葉が出たが、仲間からは「いいねぇ、ご隠居さんか。憧れるよ」で、大盛り上がり。確かに隠居の言葉には老後のショボクレ感は少ない。落語での横町のご隠居は八つあん、熊さんらから諸々の相談にのるなど、世話好きなお人良しと相場が決まっている。江戸時代、町人の隠居暮らしは商家あがりで金銭的にも余裕があり、隠居家で、三味線、音曲、盆栽、骨董集めなど風流を楽しんだ。
もとより趣味にだけ生きたわけではない。例えば数千にのぼったという寺子屋の師匠のかなりが商家の隠居だったという。読み、書き、算盤に長けている商家のご隠居にはたしかにうってつけだったろう。江戸期に来日した外国人が日本人は貧しいが、読み、書きができる知的水準の高さに驚いたとの記述がある。寺小屋の貢献度も高かったはずだ。有名人で言えば京都綿小路の青物問屋の家督を40歳で弟に譲って画業に専念した伊藤若沖、49歳で早々と家業を長男に譲り、全国行脚の末に全日本地図を作成した伊能忠敬ら隠居後にコトを成し遂げた人は数多い。
武士社会での隠居は小説やドラマになる。なかでも藤沢周平の「三屋清左衛門残日録」がいい。東北の小藩の前藩主の用人をつとめた清左衛門は離れに起臥する悠々自適の隠居の身。趣味の釣りや道場通い、時々の旧友たちとの集まりなど自らがのぞんだ暮らしだ。親友の町奉行などから持ち込まれた種々の事件を衰えない剣術の腕前と推察力で解決していく。老いの恋心も交じる。真摯に生きる日々を、「残日録」と名づけた日記に綴る。藤沢文学の真骨頂である世情の機微がしっとりと描かれる。ただ、その中でもけやきの老木に自らを重ねて思う。「日残りて昏るるに未だ遠し」。そう。この言葉に我らロートルたちは万感の想いをつのらせるのだ。
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
一般社団法人工務店フォーラム 災害に強い家づくりセミナー 第3回「いつまでもケガをしづらい家づくり」
2025.06.18
-
【住宅業界関係者向け】フォーリンラブ・ハジメの釣り教室
2025.06.09
-
アキレス・シネジック 熱中症・水害・台風から身を守る防災術
2025.06.09