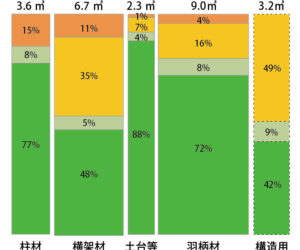マーケット獲得へ地域格差解消を
問われる、乾燥材の供給力
利用期を迎える国産材を活用して林業の成長産業化に導くにはどのような取り組みが求められているのか。
林材ライターの赤堀楠雄氏が地域で芽生える国産材活用の事例をルポする。
乾燥能力が不足していた
ウッドショックで木材が不足する中、国産材の供給が間に合わなかったのにはいくつかの理由があるが、地域によっては、乾燥材の供給体制が整っていないことが影響したケースがあった。供給量を増やそうにも乾燥が間に合わず、殺到する注文に対応することができなかったのである。
もともと生産量に余裕があるわけではないので、急な注文に応えられない──と言えばもっともらしく聞こえる。だが、乾燥材に関するこのケースは事情が異なる。生産量に余裕がないのではなく、生産能力が不足しているという根本的な問題があった。
ウッドショックで品薄になったベイマツ、SPF、ホワイトウッド、レッドウッドは、ベイマツの一部製品を除けば、いずれも乾燥材として流通し、利用されている。それらをスギやヒノキ、あるいはカラマツで間に合わせようとしても乾燥材が出てこない。不足感は一向に解消されず、相場が急騰する事態となった。
乾燥材は2000年以降に普及

国産材の供給体制に関して、乾燥材への対応を強化する必要性は20年以上前から強調されてきた。背景にはプレカットの普及がある。
国内で製材品の乾燥にいち早く取り組んだのは、製材最大手の中国木材で、1980年代末から乾燥材の生産に着手した。当時の同社は米材専門メーカーで、その後、同社の定番商品となり、在来工法用の梁材の代名詞にもなっている乾燥平角「ドライビーム」を89年に発売した。
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催
2026.02.05
-
AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説
2026.02.02
-
リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説
2026.01.29