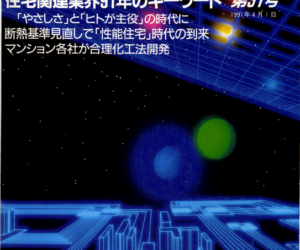都市農地と住まい【前編】
東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 安藤光義
都市農地の減少にどう歯止めをかけるか
緑地減少は住環境にも悪影響
2022年に大量の生産緑地が指定解除になる、いわゆる2022年問題への注目度が増している。一方国は、持続可能な都市経営の観点から、都市農業を再評価し、都市農地を保全・活用しやすくする制度改正を進める。こうした制度改正は、どのような影響をもたらすのか。都市農業・農地政策に詳しい東京大学大学院農学生命科学研究科の安藤光義教授に伺った。
──生産緑地の2022年問題への注目度が高まっています。そもそも生産緑地制度とは、どのような目的で導入されたものなのでしょうか。

バブル期に都市部の不動産価格が高騰する中で、宅地供給を増やすため、農地として保存すべき農地は保全し、その他の農地は宅地への転用をより進めていくという姿勢をより明確にする形で、1992年に生産緑地法が改正されましたが、私は「都市に農地はいらない」と宣言した制度改正であったと思っています。
三大都市圏の市街化区域内農地が相続税納税猶予制度の適用を受けるには生産緑地の指定を受けることが条件になりました。農地面積が500平方m以上、そして30年間、農地として維持することが条件で、かつ、相続税納税猶予を受けた場合には、終身営農が条件とされました。噛み砕いていえば、「農地を吐き出せ、そうしないと重い税金をかけるぞ。そして納税猶予を使って農地を守るのであれば、あなたの代では転用できませんよ」ということだったわけです。宅地化農地か生産緑地か踏み絵を踏ませた結果が大量の宅地化農地の選択だったわけです。生産緑地の指定は、全体の3割程度でした。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
(一社)リビングアメニティ協会 「健康×省エネ×快適をつくる断熱リフォーム」を解説するセミナー
2026.02.09
-
ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催
2026.02.05
-
AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説
2026.02.02