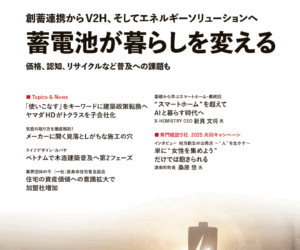東京都がアフォーダブル住宅運営で4事業者を選定 100億円を出資、26年度以降約300戸供給
Housing Tribune Weekly vol.753
東京都が「官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンド」運営事業者候補を選定した。6月からファンド運営者の募集を開始し、調査を実施した上で、同10月に選定委員会による審査で候補者を決定した。東京都都は少子化対策の一環として、子育て世帯が住みやすいアフォーダブル住宅の供給推進を掲げる。今回のファンド形成により、新たなモデル構築や民間主体での供給機運の醸成を目指す。
選ばれた事業者は、①SMBC信託銀行、墨田区で子育て支援賃貸マンション「ネウボーノ」を展開する萬富、②野村不動産、野村不動産投資顧問、③三菱UFJ信託銀行、再生した空き家を賃貸住宅として供給する事業を展開するヤモリ、④りそな不動産投資顧問、マックスリアルテ ィー、名古屋市でシングルマザー向けのアフォーダブル住宅を供給するLivEQuality大家さん、の4つのコンソーシアム。①②は、投資対象を新築マンションとして、子育て支援をテーマに市場家賃の80%程度で貸し出す。③は中古戸建の空き家を活用して賃貸住宅を供給し、市場家賃の80%程度で貸し出す。④は、ひとり親や子育て支援をテーマに既存・新築マンションを投資対象とし、市場家賃の75%程度での賃貸を目指す。今後、各コンソーシアムと詳細な内容を調整後、ファンド契約を締結。今年度内に東京都から各ファンドに対し合計100億円の出資、26年度以降、順次住宅供給を開始し、全300戸のアフォーダブル住宅供給を見込む。入居対象は、18歳未満の子を養育する子育て世帯であり、住居の広さはひとり親など世帯人数の少ない世帯を除き、原則45㎡以上の住戸としている。入居者選定は各事業者に委ねる方針だ。
経済協力開発機構(OECD)による「アフォーダブル住宅」の定義は、低所得・中間所得世帯の所得水準でも、経済的に手が届く価格の分譲住宅・賃貸住宅とされている。日本では、特定のルールにより住宅確保要配慮者に割り当てられた公営住宅といったセーフティネット住宅はあるものの、より広い層に向けた住宅支援であるアフォーダブル住宅の定義、支援制度が実質的には存在していなかった。
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
リフィード 社員リレーによるオンラインセミナー「リフィードのこぼれ話」いよいよ後半へ
2026.02.16
-
硝子繊維協会 住宅の設計・施工者に向けた特別セミナーを開催
2026.02.16
-
(一社)リビングアメニティ協会 「健康×省エネ×快適をつくる断熱リフォーム」を解説するセミナー
2026.02.09