人の流れが地域活性化を支えるシェアリング時代の地方創生
国土交通省 不動産業課長 倉石誠司 氏
石破内閣の肝いりの政策であり、地方創生の最後の切り札ともいわれる「二地域居住」。
移住、観光と異なる二地域居住の可能性とは何か。地元、島根県松江市で「公共交通で暮らしやすい未来を実現するプロジェクトチームアドバイザー委員」なども務め、地方創生をライフワーク的に取り組んでいる国土交通省 不動産業課長の倉石誠司氏に二地域居住の可能性について伺った。
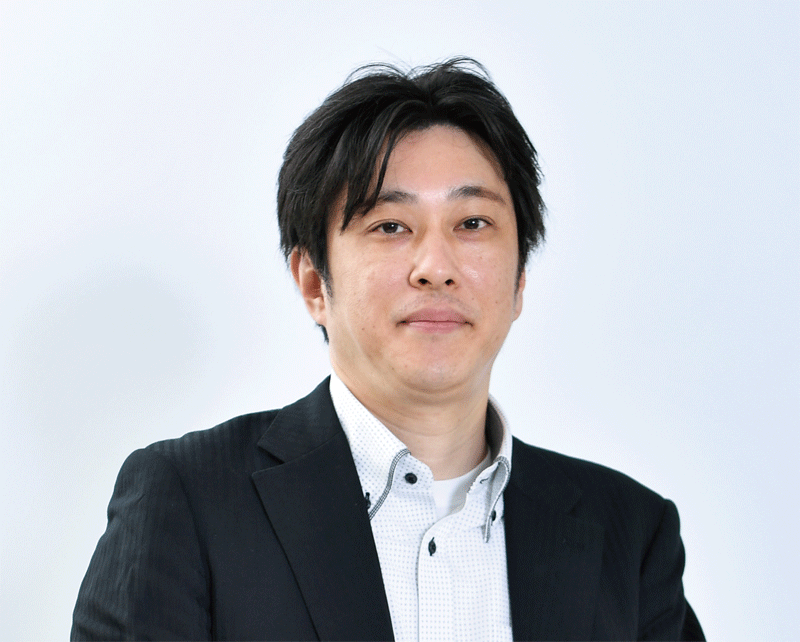
倉石 誠司 氏
国土交通省 不動産業課長
倉石 誠司 氏
1976年、島根県松江市生まれ。1999年建設省(現・国土交通省)入省。2003年英国留学、地域都市政策の分野で修士号取得。その後、国交省では大臣官房、総合政策局、不動産・建設経済局、都市局、道路局、住宅局などを経験。2023年7月~今年6月まで国土政策局総合計画課長。今年7月より不動産業課長に。筑波大学の客員教授(非常勤)も務める。
避けては通れない人口減少
人も暮らしも〝シェア〟する時代に
2023年に第三次国土形成計画が閣議決定されました。これを基に、ビジョンづくりだけではなく、国土交通省でもできることをやろうと、実装第一弾として始めたのが二地域居住の取り組みです。23年秋には二地域居住促進法の専門委員会を立ち上げ、24年2月に国会に法案を提出、11月に施行しました。
二地域居住の話をするうえで、外せないのが日本の人口減少についてですが、日本の総人口は2008年にピークを迎え、減少局面に入ってから10年以上が経っています。2050年には概ね1億人程度になると考えられています。23年の第三次国土形成計画では、人口減少について正面から捉えた表現はありませんでした。しかし、そこからの2年間で、政策づくりにおいては、人口減少を正面から受け止めようという考え方になっています。
石破首相は今年1月の施政方針演説で、「令和の日本列島改造」を掲げ、一丁目一番地として、二地域居住の支援を訴えました。また、発言の中で「都市対地方の二項対立ではなく」という言葉もありましたが、これは国交省としても同じ考えです。これまでの10年間の地方創生政策で、都市から地方への移住一辺倒では、限界があるということが分かりました。都会か地方かの2択では、都会と地方、あるいは地方と地方で人の取り合いが起き消耗戦になります。
二地域居住が目指すのは都会と地方のどちらかに住むのではなく、どちらにも暮らしがある状態です。これにより人の往来ができることで、住民票上の人口が減っても、地域に係る人口の総量は無限に増えていくのではないかと思います。
コロナ禍などを経て、特に若い人たちの価値観が大きく変化しています。ひとつのものに固執するのではなく、複数の選択肢を持ちながら、状況に合わせて一番良いものを選んで人生を楽しもうという方が増えている。
一方で、シニア世代が仕事を引退した後の生活についても、選択肢を増やす必要があります。
二地域居住促進法を施行したところで、二地域居住の事例が急に増えるとは思っていません。人の価値観にもかかわる部分ですので、少しずつ着実に進めていく必要があると思います。
二地域居住の負担軽減で「ふるさと住民制度」など検討
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術
2026.01.15
-
CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催
2026.01.15
-
フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説
2026.01.13



