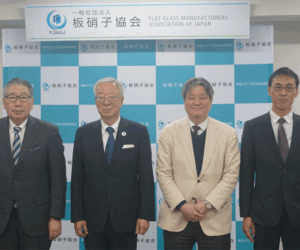林業を経営しているのは誰か? 費用負担の在り方を整理すべき
林業の経営収入といえば、木を伐採して販売した代金のことだろうと思い浮かぶ。ところが、木材価格が低下したため、木の販売代金で生計を立てるのは難しくなった。そのため、森林の所有者である林家が林業経営者としての立場を実質的に失う事態となっている。では、林業を経営しているのは誰なのか。
林家の手取りは激減
山の木を販売した際の林家の手取りは、丸太の販売代金から伐採・搬出などにかかった経費を差し引いた残額ということになる。これを立木代金あるいは立木価格と呼ぶ。
日本不動産研究所が毎年実施している調査によると、スギの立木価格(各年3月末時点)はピークの1980年には2万2707円(1㎥当たり。以下同じ)だったが、その後は長期間下落し続け、1998年には9191円と1万円台を割り込み、2013年には過去最低の2465円まで値下がりした。その後、多少値戻しして直近の2024年には4127円となっているが、ピーク時より1万8000円も安くなっている。
立木価格が低迷しているのは、丸太価格が値下がりしたためだ。農林水産省の調査(「木材価格」、「木材需給報告書」)によると、スギ中丸太(直径20㎝程度)の価格は1980年には3万9600円だったものが、2024年には1万5900円と2万4000円も値下がりしている。
皆伐収入は700万円減/ha
こうした丸太と立木の大幅な値下がりは、林業の経営構造を大きく変化させた。
50年生程度のスギ人工林1haを皆伐した際の生産量を400㎥と仮定して林家の収入を試算すると、1980年には900万円近くも懐に入っていた(400㎥×2万2707円)ものが、2024年は160万円程度(400㎥×4127円)と700万円以上も減ったことになる。
伐採跡地に再造林を行う経費は、植林後の下刈りの費用も含めると1ha当たり150~200万円程度はかかる。所有林の木を伐って得た収入から再造林の経費を支出すると林家の手元にはほとんど残らないか、下手をすると費用の持ち出しになる。
最近は再造林に手厚い補助金が支給されるので、実際にはある程度の手取りは確保できているはずだが、それでも1haを伐採したくらいでは生活するのに十分な収入を得ることはできない。伐採面積を増やせば収入も増えるわけだが、50年も育てた末の利益がわずかにしかならない構図は変わらない。
こうなると、伐採跡地に再び木を植えて育てようという気にはならない人がどうしても出てくる。ただでさえ少ない収入を目減りさせたくない意識も働き、その結果、再造林を見合わせるケースが続出しているわけだ。
労務の担い手が経営者に
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術
2026.01.15
-
CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催
2026.01.15
-
フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説
2026.01.13