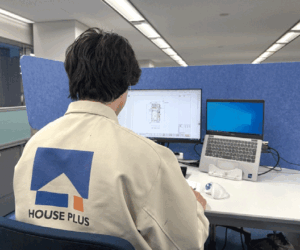被災地の景色を変える
1995年の兵庫県南部地震や2004年の新潟中越地震、直近では能登半島地震など、巨大地震による被災地へ足を運んできた。都市部、山間部、沿岸部といった場所の違いや、人口密集地や過疎地などの違い、何より地震、津波、土砂崩れなど原因によって被災地の景色は異なっていた。それでも日々の暮らしが営まれ、少しずつでも日常を取り戻していく景色も見てきた。

ミャンマーでマグニチュード7.7という大地震が発生した。能登半島地震のマグニチュード7.6を上回る規模である。すでに死者3000人超え、住宅被害も2万1783棟が確認されている(4月3日現在)。新聞やネットで倒壊した建物や瓦礫の山を前に救助活動を行う人々の写真を見るたび、これまで見てきた被災地の風景を思い出す。建物の形や人々の風貌は異なっていても、同じように被災した人がおり、救助に携わる人がいる。日本政府が派遣した国際救助援助隊・医療チームが現地で活動を開始した。これまでの大規模災害で得た経験などを発揮して欲しいと思う。
この記事はプレミアム会員限定記事です
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
料金・詳細はこちら
新規会員登録
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
(一社)リビングアメニティ協会 「健康×省エネ×快適をつくる断熱リフォーム」を解説するセミナー
2026.02.09
-
ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催
2026.02.05
-
AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説
2026.02.02