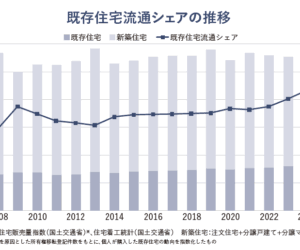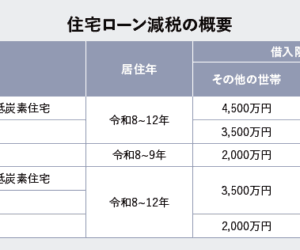30年かかり扉開く、真の耐震木造普及を加速 大規模木造建築のネットワーク形成も視野
エヌ・シー・エヌ 代表取締役社長 田鎖郁男 氏
エヌ・シー・エヌは1996年の創業時から一貫して安心・安全な独自の木構造「SE構法」を普及させ、資産価値のある木造建築物を提供することに注力してきた。法改正や物価高などの影響により住宅産業が大きく変化する中で、今後どのように事業を進めていくのか。田鎖郁男社長に話を聞いた。
―2025年4月から4号特例の縮小がスタートします。木造2階建て、200㎡超の木造平屋建ての「新2号建築物」は、確認申請の際に構造関係の図書の提出が必要となり、構造計算へのシフトが加速すると見られています。

当社は1995年の阪神・淡路大震災での大きな被害に端を発し、「真の耐震木造を普及させる」という目的で、義務ではない構造計算を行ったSE構法を広めてきました。30年かかり、やっと扉が開いたという感覚です。阪神・淡路大震災でのひどい惨状を見た心ある技術者たちは、その時点で木造の構造計算を絶対義務化すべきだと思っていました。国土交通省としても過去に何度も法改正を試みて、ようやくここに到達した。我々は法律で義務化されていなくとも構造計算を行い、安全な木造を普及させるために力一杯活動してきましたが、今回の大きな変化を全力で応援したいですし、もしお困りの方がいたら、その人たちに正しく耐震性を確保していく方法を伝えていきたいと思っています。
ただ、私たちの「法律がなくても絶対安全につくる」というスタンスは変わりませんし、法律が変わり、必要壁量や柱の太さなどが厳格化されたからといって、突然すべての木造建築が安全になるわけではありません。また、構造安全性を壁量計算など仕様規定で確認するのか、許容応力度計算など精緻な構造計算で確認するのか、そこを一緒くたに議論することは危険だと思っています。取り締まりの方法ではなく、大事なのはどうやって家をつくるかです。4号特例縮小や、省エネ基準の適合義務化がスタートすることに関わらず、我々は、今回の法改正で求められているレベルより一段高いレベルを追求して家づくりをしてきましたので、やることは何も変わりません。
―2024年1月の能登半島地震で、あらためて木造住宅の耐震性の重要性が浮き彫りとなりました。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説
2026.01.29
-
日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催
2026.01.29
-
インテグラル 「AI活用のすすめ」セミナーを開催
2026.01.28