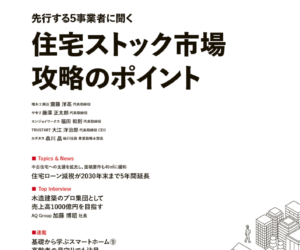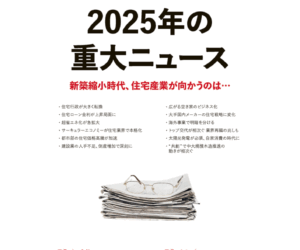心地よく恒久的に住める仮設住宅 木を使うならリサイクル・リユースまで
注目!!PROJECT「DLT恒久仮設木造住宅」(石川県珠洲市、輪島市)
新たな視点の建築プロジェクトを解説する「注目‼ プロジェクト」の第一回目は、石川県珠洲市、輪島市で、建築界のノーベル賞といわれるプリツカー賞受賞建築家、坂 茂氏が設計した「DLT恒久仮設木造住宅」だ。製材を並べ木ダボで接合するDLTを構造材として使用。DLTで組み上げたコンテナ型のユニットを市松模様に積み2階建ての集合住宅を建設する。坂氏に話を聞いた。
──「DLT恒久仮設木造住宅」のプロジェクトは、どのような経緯でスタートしたのでしょうか。
大きな地震災害が起きるたびに仮設住宅をつくっています。阪神・淡路大震災では、仮設住宅として紙管を活用した紙のログハウスをつくりました。東日本大震災では、避難所用の紙の間仕切りシステムを提供しました。また、宮城県女川町では十分な平地がない被災地に、海上輸送用コンテナを使って3階建ての仮設住宅を建設しました。避難所の紙管間仕切りシステムは、熊本地震、今回の能登半島地震でも活用されました。
世界各地で大規模災害が発生するたびに多くの人が家を失っています。また、紛争が勃発し多くの難民が発生しています。そうした人たちに仮設住宅、難民用シェルターなどを迅速にローコストにつくり提供することは、私の建築家としての活動の一環であり、世界中で取り組みを続けています。
能登半島地震の発生後も当然すぐに取り組むべきだと思いました。もともと石川県珠洲市では、「奥能登国際芸術祭2023」に合わせてオープンした「潮騒レストラン」の設計をしていたこともあり、泉谷満寿裕市長と面識がありました。市長からすぐに仮設住宅建設の相談がありました。また、馳浩県知事とお会いするチャンスもあり、仮設住宅の建設で支援したいとお話をしました。1月後半には石川県から、仮設住宅建設の公募が始まり、すぐにチームをつくり設計プランをまとめ応募しました。
過去の地震災害で仮設住宅の設計、建設に携わる中で、恒久的に使えるものをつくりたいと考えてきました。2年間で壊して被災者にまた引っ越してもらうのはあまりにも馬鹿げています。
プレハブの仮設住宅と同等の金額で、住み心地が良く、恒久的に住めるものをつくりたいと考えて実践しました。
ローテク、シンプルなDLTに着目
──今回、「DLT恒久仮設木造住宅」を設計されました。なぜDLTに着目されたのでしょうか。DLTの魅力、ポテンシャルを教えてください。
能登半島地震が発生する約2年前から、木質パネルDLTを用いたコンテナ型の仮設住宅の開発を進めていたため、今回の地震発生後、対応することができました。
以前、長谷川萬治商店にDLTを紹介してもらい、すぐにこれは木質コンテナ接合部のフィンガージョイントに向いている、仮設住宅に使えるかもしれない、と思いました。
DLTは、木材を木ダボで接合した木質パネルで、接着剤は使わずに木材に深孔をあけて木ダボを通すという簡易な方法で製造できます。製造方法がローテクでシンプルなため、各地域で中小の製材所などが地域材を活用して、大きな設備がなくてもコストを抑えてつくることができます。
スピードが求められる仮設住宅をつくる上で、大きなポテンシャルを秘めていると感じました。
コンテナのユニットを市松模様に積む
──どのようにDLTを加工し組み合わせて、コンテナ型のユニット、そして「DLT恒久仮設木造住宅」が完成するのでしょうか。
30㎜×105㎜のスギの製材の端部を櫛状にずらして木ダボで一体化することにより、コンテナを形づくるための接合部のフィンガージョイントが容易につくれるようにしました。剛接合にするために、接合部にどのようにビスを打てばいいのかを滋賀県立大学の陶器教授に提案してもらい構造試験を行いました。
その後、長谷川萬治商店の群馬・館林工場の敷地内にプロトタイプを試作し、納まりや施工性などを検証し十分に実現できることを確認しました。パネル同士を剛接合にしたコンテナ形状にした結果、コンテナ内部の壁がなくて済むという効果も生まれ、開放的な空間をつくることができました。
コンテナ型のユニットを市松模様に積むことは、東日本大震災の仮設住宅として建設した女川のコンテナの集合住宅のときからやっています。昔からコンテナを積んでいく構法はありますが、単純に積むと壁も床も二重になって無駄になるわけです。しかし、市松模様に積めば、その無駄な部分が省略でき、コンテナの数も半分で済みます。コンテナを市松模様に積む箇所に生じる段差も配管スペースとして有効で、これまでのコンテナをただ積んでいく構法とは違う利点が生まれます。
建築家の役割は、問題点を解決して、より美しく、住み心地がいいものをつくることです。
今回も住まい手のことを考えて、きちっと愛情を持って使いやすいように設計しています。厚さ105㎜のDLTは、その厚みが断熱材としても寄与します。DLTは遮音や吸音の試験を行っており、どのくらいの性能があるのかを把握し、設計しています。
アフォーダブル住宅の開発も
──住宅価格が高騰し持家市場が冷え込んでいます。今回設計された「DLT恒久仮設木造住宅」は、アフォーダブル住宅としてポテンシャルはあるのでしょうか。
いい住宅を安くつくる、アフォーダブルハウジングは、日本だけの問題ではなく、アメリカでもニュージーランドでも世界中で課題になっています。「DLT恒久仮設木造住宅」の構法は、日本以外でももちろん活用できます。世界中に広げていきたいですね。
今回、能登で建設した「DLT恒久仮設木造住宅」では、仮設住宅の基準に基づき、6坪、9坪、12坪の空間をつくりました。今後は、一般家庭向けのプランや商品をつくれればと思います。
住宅の設計は一番の訓練
──坂さんにとって、住宅を設計することは、どのような意味を持つのでしょうか。
住宅の設計は、大きな建築物を設計するよりも難しい仕事です。
オフィスやマンションは、一般的な回答を見つけ出して設計することができますし、プランを繰り返し使える場合もあります。対して住宅は、一人ひとりのクライアントの生活スタイルや価値観に合わせてつくる必要があり、また、プランの繰り返しもありません。
自分自身にとっても、スタッフにとっても一番の訓練になると思っています。新しいアイディアが生まれた時には、まず住宅レベルから始めて確認した上で、さらに大きなスケールに広げていきます。
無駄にするなら木を使う意味はない
──建築材料としての木材をどのように見ていますか。脱炭素の流れの中で、木造建築推進の気運が高まっています。
そうした流れとは関係なく、昔から木材は使っており、紙の建築も環境問題が起こる前から開発し使っています。身の回りにある材料で何ができるか、特に活用に制約がある木や紙を使い、弱いものを弱いなりに工夫して使って建築を成立させることに興味があります。木をどんどん建築に使おうという木造推進のブームは悪いことではないと思います。ただし、木を使う知識がないのに流行りで使うことは問題です。私が紙の建築を開発したのは短期的な展覧会のイベントにわざわざ木材を使って捨てるのがもったいないと思ったので、紙管を使うことを思いついたわけです。今回の大阪万博のように木材を仮設に使うのであれば、仮設として使用した後にどうするかまで考える必要があります。
2000年のドイツ・ハノーバー万博のとき、私は日本館のパビリオンを設計しました。万博のテーマ自体が環境問題だったので、建物を解体した後にほとんどの材料をリサイクルしたり、リユースできるように、材料の仕様や構法を選択しました。パビリオンを紙管などでつくり、解体後は、ドイツの紙管メーカーにそれを引き取ってもらいリサイクルするというところまでを契約に入れてプロジェクトを進めました。ハノーバー万博では、スイスの建築家ピーター・ズントーが木を使いスイス館のパビリオンを設計し、やはり解体した後の使い方を考えていました。万博は短期間で閉幕することが分かっています。いかにリサイクル、リユースを前提に設計するかが、デザインの大きな要素になります。
さらに言えば、1889年にパリ万博のために建てられたエッフェル塔は、未だにモニュメントとして使われています。1967年のモントリオール万博のときは、フライ・オットーが設計したマストで支えられたケーブルネット吊構造の西ドイツ館、また、バックミンスター・フラーが設計したジオデシックドームのアメリカ館など、次の時代を切り開く新しい技術を駆使したパビリオンが注目されました。1970年の大阪万博で注目を集めたアメリカ館の巨大エアドームは、その後、エアドーム型の球場が普及するきっかけとなり、東京ドームも生まれているわけです。もともと万博はそうした実験の場でした。鉄はどんな形にもしてリユースできますが、木材はそうはいきません。木材はどんどん使うべきですが、無駄にするべきではない。無駄にするなら木を使う意味はないと思います。
汎用性の高い構法を開発 仮設住宅の新しいモデルに

建築家 坂 茂氏
2024年6月、珠洲市の公園内に、坂 茂氏が設計した恒久的に使える仮設住宅、木造の2階建て集合住宅が完成した。この仮設住宅の構造材としてスイスで考案され、長谷川萬治商店が国内導入し製造している木質パネル「DLT」が使用された。DLTは、製材を並べ木ダボで接合した木質パネルで、接着剤は使わずに木材に深孔をあけて木ダボを通すという簡易な方法で製造できる。製造設備が不要で、中小の製材所なども地域材を活用してコストを抑えてつくることができる。
こうしたDLTの特徴に坂 茂氏が着目し、製材をずらして凹凸にダボで固定することにより一切加工せずにフィンガージョイントをつくることを考案した。約2年前から坂茂建築設計のリードでDLTを使った仮設住宅を検討してきた。23年には、長谷川萬治商店の群馬・館林工場の敷地内にプロトタイプを建設し技術検証を進め、陶器浩一 滋賀県立大学 環境科学部教授らに協力してもらいDLTコンテナ型(カルバード状)ユニットの構造安全性を検証し十分な構造強度を持つことも確認していた。
そして24年1月1日、能登半島地震が発生。プロトタイプの開発、検証を進めていた実績を踏まえて、3月から「DLT恒久仮設木造住宅」を実際に建てるプロジェクトが急ピッチのスケジュールでスタートした。まず館林工場に、全国各地からスギ材を集め、製造シフトを増やすことで通常の数倍の稼働ペースで大量のDLTを製造し珠洲市に搬送した。
珠洲市に搬送された幅30㎝×長さ約3mのDLTは、パネル上下の端部が「櫛の歯」のようにすでに工場で加工されている。現場で施工者がそのフィンガージョイントがかみ合うように接合しビスで固定しDLT枠をつくる。さらに、クレーンを用いてこのDLT枠を持ち上げ、鉄筋コンクリートの基礎の上に建てていく。基礎とDLT枠はプレートで固定する。この工程を繰り替えし行うことで、コンテナ型のユニットが生まれる。このコンテナ型のユニットを市松模様に積み上げ、2階建ての集合住宅を建設する。コンテナ型のユニットには大開口のサッシを入れることで開放的な空間を創出した。
珠洲市で完成した「DLT恒久仮設木造住宅」は、1棟当たり6坪、9坪、12坪の間取りを組あわせた15世帯の住戸からなる。珠洲市では9棟135世帯を建設する計画だ。さらに、輪島市においても3棟31世帯の建設を進めている。2年間、仮設住宅として利用した後は、復興住宅として継続使用できるように計画している。
倒壊家屋から能登瓦・古材を回収
次の人へ橋渡し 奥能登の町並みを将来へ

坂 茂氏のリードの元、大学生ボランティア、地域の人々と共に、倒壊した家屋から能登瓦や、柱や梁といった古材を回収して利活用する取り組みも行っている。能登瓦を製造する会社は数年前に閉業し、新しく製造できる会社はない状況になってしまった。奥能登を象徴する能登瓦の町並みを将来へとつなげるために、公費解体で粉砕されて処分される前に倒壊家屋から瓦や古材を回収し、次の人への橋渡しを行う取り組みだ。
また、「奥能登には江戸の末期から明治ぐらいに建った素晴らしい民家がたくさんある。今回の地震で半壊した家のオーナーは費用的に直せないと公費解体を申請している。そうすると全部ブルドーザーに引かれて粉々になり、立派な家が無駄になってしまう」(坂氏)と、それらを移築して旅館などとして使用するプロジェクトもスタートしている。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術
2026.01.15
-
CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催
2026.01.15
-
フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説
2026.01.13