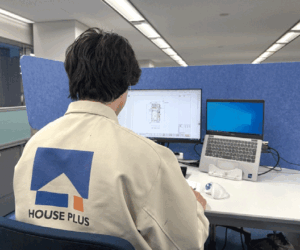環境省・Nature/関西電力・Looopが効果を実証 “上げDR”導入阻むネックとは
自動制御が効果大も社会実装にはさまざまな課題が
再生可能エネルギーの導入拡大で増える余剰電力の活用に向けて、昼間に電気を使う“上げDR”が注目される。
環境省が行った実証実験で、自動で機器を制御する方法による効果が高く、消費者メリットも大きいことが分かったが、同時にさまざまな課題も浮き彫りになった。
HEMSを活用した住宅用のエネルギー機器の自動制御が、手動制御に比べて高い「上げDR」効果があり、最大約2400円程度の消費者便益を得られる可能性があることが環境省が行った実証実験で明らかになった。一方で、市場連動型の電気料金プランでなければ経済的なメリットが出ない、自動制御に対応する機器が市場で普及していないといった課題も浮き彫りになった。
この実証は、環境省が「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)の一環として行った昼の電力需要創出に向けたモデル事業。Nature/関西電力、Looopが、それぞれ昼の電力利用へのシフトに向けた効果や消費者の利益・利便性について検証を行った。
環境省は「デコ活」の活動として、衣食住、職、移動、買い物といった暮らしの全領域を7つの分野に分けて生活者の行動変容を促す取り組みを進めている。その分野の一つが「情報(教育・ナッジ)、インセンティブ」だ。消費者や働き手にとっての行動成約要因として、①行動変容のベースとなる気候変動などの理解や関心が十分とは言えない、②行動変容の意欲を高め、また実践を促すインセンティブを受ける機会が質・量ともに不十分、③実際の行動変容を後押しする効果的な気付き(ナッジ)を与えられる機会が質・量ともに不十分、という3点を指摘し、それぞれのボトルネック解消に向けた対策を進めていく。
今回の実証は、その取り組みの一環。「すべての生活領域で、どのような行動を選択するとどれだけの効果が得られるかという情報や行動変容が促される経済的・社会的なインセンティブを、持続的かつ分かりやすい形で国民・消費者に提供する」という対策の一つとして「市場と連動したディマンドレスポンス」、特に「上げDR」の効果について実証を行った。
「上げDR」とは、昼間に電力需要を創出すること。エネルギー基本計画で再生可能エネルギーを主力電源として位置づけ、その普及拡大が進められている。しかし、再エネのなかでも主軸となる太陽光発電は昼間のみの発電で、その発電量も気象条件によって大きく左右される。一方で、電気は需要(消費量)に対して常に供給(生産量)を一致させる必要がある。そのバランスが崩れると、最悪の場合、多数の発電機が運転できなくなり大規模な停電に至る可能性さえある。つまり、再エネの導入量が増えるほど、春・秋を中心とした需要が少ない時期に再エネの発電出力が大きくなり余剰電力の発生によるリスクが高まるということだ。また、経済産業省のデータによると、再生可能エネルギーの発電量が増え続けるなか、年間約19億kWhと約45万世帯分の年間電力使用量相当が捨てられている(出力抑制)という。
この余剰電力を有効活用しようというのが「上げDR」だ。DR(ディマンドリスポンス)とは、消費者が賢く電力使用量を制御することで電力需要パターンを変化させること。「上げDR」とは、発電量が増える時間帯に設備機器を稼働させて電気を消費したり、蓄電池やEVへ充電するなど、電気の使用時間を昼間にシフトすることを指す。
今回の実証は、消費者が自ら行動する「行動変容型DR」と、機器を自動的に遠隔制御する「機器制御型DR」の2つの「上げDR」の効果を検証した。例えば、ヒートポンプ給湯器の沸き上げを、指定時間に居住者自ら行うのが「行動変容型」、遠隔制御で自動で沸き上げるのが「機器制御型」だ。
それぞれメリット・デメリットがあり、「行動変容型」は追加の機器やシステムが不用で簡単に実施が可能な一方、居住者が手動で行うため確実なシフトにつながりにくい、「機器制御型」は居住者が意識せずとも確実に実行できるが、機器制御型DRに対応している機器が十分普及していないことなどが指摘される。
PVの有無が「上げDR」成功を左右
【Nature/関西電力】
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説
2026.01.29
-
日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催
2026.01.29
-
インテグラル 「AI活用のすすめ」セミナーを開催
2026.01.28