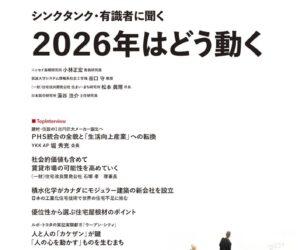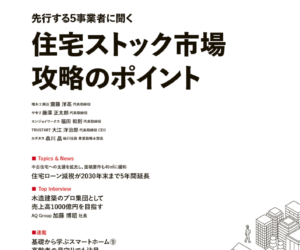太陽光パネル リサイクルの現在地
再エネが主電力の時代に使用済みパネルの行方は?
カーボンニュートラルの実現に向けて加速する住宅業界での取り組み。住宅の断熱化と並んで重要なポイントとなるのが再生可能エネルギーの導入であり、なかでも大きな役割を期待されているのが太陽光発電だ。ただ一方で、使用後の太陽光パネルについて懸念の声もあがっている。最終的な資源活用を見越したうえでの、太陽光パネルの設置が求められる。
2021年8月、国土交通省、経済産業省、環境省の3省合同による「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」がロードマップをまとめ、30年時点で「新築戸建て住宅の6割に太陽光発電設備の導入」という目標を打ち出した。同年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」では、再生可能エネルギーについて、「最優先の原則で取り組み~最大限の導入を促す」と位置づけ、「さまざまな課題の克服を野心的に想定した場合」に30年度における全電力に占める再エネの割合を36~38%、このうち太陽光発電を14~16%と見通した。太陽光発電は、それまでの見通しの約2倍である。
こうしたなか、社会的にも大きなインパクトがあったのが東京都の動き。都は22年12月に延べ床面積2000㎡未満の住宅を含む新築の建物について太陽光発電の設置義務などを含む条例改正案を可決した。これは建築主ではなく、一定以上の供給戸数のある事業者が対象であるものだが、全国初の”義務化”の取り組みが大きな注目を集めた。
太陽光発電の導入が急速であるがゆえ、さまざまな課題や不安が表出している。その一つが廃棄・リサイクル問題だ。
東京都の条例改正には賛否両論の多くの声が上がったが、パブリックコメントの公募に寄せられた主な意見の一つが廃棄・リサイクルに関するもの。「廃棄・リサイクルを含め将来的な負担が分からない」、「太陽光パネルはリサイクルできるのか」、「廃棄の際に有害物質の漏出は?」などである。太陽光パネルの寿命は20~30年程度。寿命を迎えた時、大量に出る使用済み太陽光パネルの処理をどうするのかというわけだ。
太陽光発電設備はリサイクルが可能であり、首都圏においても複数のリサイクル施設が稼働している。ただ、これらは事業用太陽光発電設備についてのものがほとんどで、都は22年度に関連する事業者による協議会を立ち上げ、住宅用太陽光発電設備のリサイクルルートの確立への取り組みを進めている。
(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の推計では、太陽光パネルの年間排出量は35~37年頃にピークを迎え、年間約17万~28万tが排出されるという。これは産業廃棄物の最終処分量の1.7~2.7%に相当する量だ。12年に始まった太陽光発電電力の固定価格買取制度(FIT)の買取期間20年を終了した太陽光パネルの排出が一斉に始まると予測する。
住宅の太陽光発電搭載が広がりつつあるなか、将来のリサイクルという課題に向けた取り組みが急ピッチで進む。
大企業から海外ベンチャーまで
続々とリサイクル事業に参入
浜田(大阪府高槻市、濵田篤介代表取締役)は太陽電池製造装置や太陽光パネル検査装置の製造を行うNPC(東京都台東区、伊藤雅文代表取締役社長)と共同で、NEDOの太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクトに申請、16年に採択を受け、太陽光パネルのリサイクル技術の開発に乗り出した。その後、21年に京都PVリサイクルセンター(京都府八幡市)を開設し、本格的にリサイクル事業をスタート、リサイクルの実績は4万枚に上る。
同社は、もともと産業廃棄物の分別やリサイクル事業を行っており、新規事業を開拓するうえで、FIT制度などで市場が勢いづいていた太陽光設備に目を向けた。同社は、浜田電気工業のスクラップ部門が分社化してできた会社で、創業者が電気工事会社を経営していたことも太陽光パネルのリサイクルに取り組むきっかけのひとつになった。
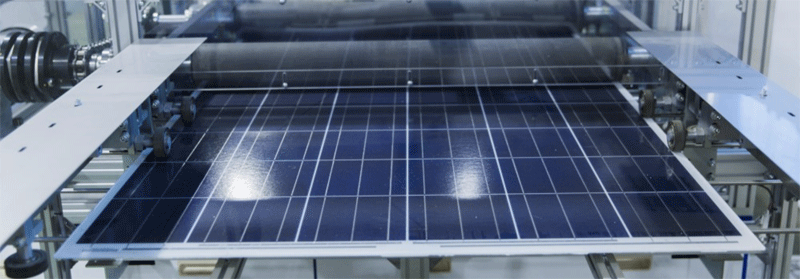
リサイクルにあたっては、NPCのホットナイフ技術を用いて、300度に熱したナイフでガラスと電池部分のセルシートを分離する。高い精度で分離できることが特徴で、異物混入を起こさないためリサイクルに回しやすい。セルシートはその後、粉砕処理をして、粒度分別後に売却、ガラスはグラスウールなどのガラス原料として再利用する。
25年度の事業化を目指して準備を進めているのはトクヤマだ。同社は19年にNEDOと共同開発を開始、北海道の空知郡南幌町に研究棟を建設し開発を始めた。北海道は太平洋側の積雪が少ない地域にメガソーラー発電所が多く存在する。一方で、太陽光パネルのリサイクルを行っている事業者はこれまでいなかったため、事業の展開に適していると判断した。
開発した低温熱分解法は、純度の高いガラスを取り出せることが強みだ。太陽光パネルのモジュール部分は、耐久性を高めるために、ガラス、樹脂(EVA/PET)、セル、リボンが強固に結合しており、分離が非常に難しい。一般的に加熱処理であれば、様々なパネルに対して汎用性が高いうえにガラスを板状で回収できるが、単純な熱分解ではガラスがすすで汚れてしまう。低温熱分解法はセラミックフィルタの上にパネルをセットし、封止材である樹脂(EVA/PET)を溶融することで、すすを発生させずガラス、セル、リボンをそれぞれ回収できる。熱分解炉は工程ごとにステーション1から3に分かれているが、すべての工程を合わせてもパネル1枚の熱分解にかかる時間は12分ほどと短時間で分解することが可能だ。また、熱分解炉のエネルギーの一部に、溶融した樹脂(EVA/PET)の燃焼熱を利用しガス消費量を低減する。
さらに、業界唯一、アルミ枠とジャンクションボックスの取り外しからセルの素材分離までを全自動化している。人手不足への対応に加え効率性の面で競争力があるとし、年間10万8000枚のパネル処理を計画している。
海外から事業参入する会社もある。
リセットカンパニー(日本事務所:東京都港区、ジョン・ソンデ代表)は韓国と日本で、太陽光パネルの洗浄ロボットを開発・販売している会社。太陽光パネルの洗浄ロボットを販売する中でその増加を感じ、今後は廃棄への対応が必要になると、2年前から韓国の補助金制度を利用してリサイクル事業の確立に向けた取り組みを行ってきた。
同社は、10月末に韓国で民間企業として初めて太陽光パネルの物理的な分離からナノシルバーの抽出まで行うリサイクル工場を稼働、運用を開始している。
日本においては拠点が確立していないため、現段階では自社で開発したリサイクル機器をリサイクル事業者などに販売しており、同社の装備に興味を持っている会社と契約に向けて検討が進んでいるという。今後は、鹿児島県と大阪府に所在する同社とリレーションのある企業の工場に装備を導入し、実績を積んでから自社工場を持つ計画だ。

同社の装備の特徴は、セル/EVAシートに含まれる銀をナノサイズで取り出せることだ。
分離後のセルシートを酸性溶液に溶かし、パルスレーザーを用いた太陽光還元技術でナノシルバーを抽出する。ナノシルバーは、通常の銀に比べ約10倍の価格で売却できるため、大きな強みとなっている。また、近年増加傾向にある両面で発電を行う太陽光パネルにも対応している。両面型の場合は、ジャンクションボックスの位置が異なるが、同社の装備はジャンクションボックスの位置を認識して、自動で制御、分離作業を行う。
ガラスの活用が最大の課題
適正なリサイクルへ協会の設立も
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
ジャパンホームシールド、AI活用の空き家流通・不動産参入戦略ウェビナーを開催
2026.02.05
-
AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説
2026.02.02
-
リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説
2026.01.29