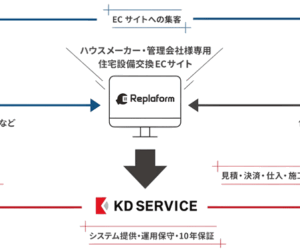デジタルで変化する防災
データ集約による効率化などが進む
甚大化する自然災害を前に、過去の教訓を生かし、災害対策の課題を解消していく必要がある。
デジタル技術が発達するなかで、防災のかたちはどのように変わっていくのか。
台風の大型化や集中豪雨の頻発など、自然災害が甚大化している。全国の1時間降水量100㎜以上の平均年間発生回数は、統計期間の最初の10年間(1976~85年)と最近10年間(2013~22年)でおおよそ2倍に増加している。さらに、今後30年以内には首都直下地震や南海トラフ地震といった大地震が7~8割の確率で発生するとの予測も出ており、防災力の強化は喫緊の課題となっている。
一方で、社会の変化としてはIT技術の進化が目まぐるしい。スマートロックの普及や不動産取引の電子契約の解禁、生成AIによる顧客対応―。こうしたデジタル技術の採用が進むのは、防災の分野も例外でない。

政府は、令和5年版防災白書で、防災におけるデジタル技術の活用などについて①災害時の情報の集約化、②被災者支援システムの構築、③デジタル・防災技術ワーキンググループでの提言を踏まえた対応、の3つの項目で取り組みをまとめている。
なかでも、情報の集約化では、災害時において行政と民間がそれぞれ所有している被害状況や避難者の動向、物資の状況などの情報共有が重要だとし、内閣府は17年度から「国と地方・民間の『災害情報ハブ』推進チーム」を設置、情報の共有を図るために効果的な手段と考えられるデジタル技術の活用、関係機関間における情報共有の方法や期間などのルール及びこれを通じた情報のやりとり(災害情報ハブ)の推進に向けて検討を進めてきた。
19年度からはISUT(Information Support Team、アイサット)という大規模災害時に被災情報や避難所などの情報を集約・地図化・提供して、地方公共団体などの災害対応を支援する現地派遣チームの運用を開始。被害状況や災害廃棄物の情報など、事前にデータで共有する体制が整えられない動的な情報を収集・整理・地図化し、電子地図を表示するためのサイトである、ISUTサイトにおいて体系的に整理するとともに、指定⾏政機関・地⽅公共団体・災害対策基本法に基づく指定公共機関へ共有することで、災害対応機関の迅速かつ的確な意思決定を支援する。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術
2026.01.15
-
CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催
2026.01.15
-
フクビ化学工業 2026年度の断熱改修の補助金税制をウェビナーで解説
2026.01.13