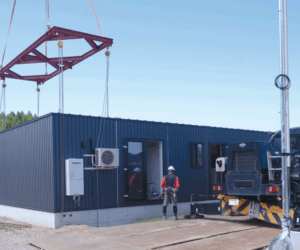【検証・熊本地震】二度の大地震が突き付けた課題
なぜ、新耐震以降の建物も倒れたのか?
4月14日、16日に発生した熊本地震では、前震と本震という2つの大きな揺れにより、新耐震基準以降に建てられた木造住宅にも建物被害が広がった。
今回のような想定を超える巨大地震が発生した場合、現行の耐震基準ぎりぎりのレベルで建てられた建物では、一定の割合で全壊や倒壊の建物被害が生じることも浮き彫りになってきている。
建築基準法をクリアしていれば安心・安全という考え方を改め、巨大地震にも対応できる地震対策の見直しが求められている。
建物被害の原因分析を開始 不十分な接合仕様などが影響か
今回の熊本地震により建物被害が集中した益城町、西原村、南阿蘇村などでは、前震で著しいまでの被害を受けていなかった建物が本震により被害を著しく拡大したと見られている。
とくに益城町役場で記録された本震の地震波(加速度)を見ると、建築基準法で想定している倍以上の地震波が観測された。被害が集中した益城町は、洪積台地と丘陵に挟まれた、楔形に入り組む軟弱地盤の低地だった。こうした地形は、地震波や津波を増幅させる特徴があり、観測された震度よりも、さらに大きな揺れが発生していた可能性も指摘されている。さらに、木造住宅に被害を与えやすいと言われる周期1~2秒の地震動が発生したことも建物被害に拍車をかけたと見られている。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
ジャパンホームシールド 2026年住宅市場予測オンラインセミナーを開催
2025.12.05
-
CLUE 住宅事業者向け“営業の工夫”セミナーを開催
2025.12.04
-
リフィード リフォーム人材戦略セミナーを開催
2025.11.25