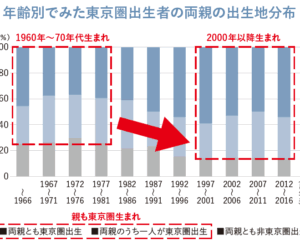歌舞伎がなくなる危機感に襲われた 10代目松本幸四郎がコロナ禍の歌舞伎を語る
史上初の「図夢歌舞伎」で映像歌舞伎の新たな道を踏み出す。 変わる歌舞伎、変わらない歌舞伎
新型コロナの感染が始まってから半年余、今なお苦悶の声は絶えないが、特にライブエンターテイメント界の打撃は大きい。400年の歴史を持つ伝統芸能、歌舞伎も例外ではなく、「もう歌舞伎はなくなってしまうとの夢さえ見た」と、コロナ下での苦しい胸の内を日本記者クラブで語ったのは歌舞伎俳優の10代目、松本幸四郎。3月公演の中止から始まって4月、5月と無為に過ごす中、「最初の1か月間、一歩も外に出なかった。稽古をする気にもなれない」「役者として何もできない無力感にさいなまれた。次あるものがない、何をしていいかわからないという状況はつらかった」と振り返る。

だが、コロナ感染が長期化する中、「もう元には戻らないだろう」との思いは強く、「このままでは本当に歌舞伎はなくなってしまう。何かしなくては、環境の変化に対応して歌舞伎も変わらなくては」の切羽詰まった思いに駆られる。舞台の幕が上がらなくては、芝居にかかわる音楽、衣装、床山、大道具、小道具など、多くの人の生活もさることながら、それぞれがスペシャリストである人たちの技が鈍りかねない、そのために何とか働く場を作りたい、の気持ちが募った。
発案したのがオンライン会議システムのZoomを使った「図夢歌舞伎」だ。「芝居、芸を見てもらいたいの一心」でつくり上げ、8月25日に史上初のオンライン専用の作品として「図夢歌舞伎忠臣蔵」を上演、配信した。新しい歌舞伎の形として注目を浴び「劇場での生の歌舞伎とオンライン配信による歌舞伎とが両立できる」との手ごたえも得たようだ。
シネマ歌舞伎や舞台中継による歌舞伎の映像化はあるが、TVドラマのように日常生活の中に映像化された歌舞伎が入り込むことはこれまでなかった。「文化は日常生活の中にあってこそ」の思いは以前から持っていたそうで、その意味でコロナ禍での苦肉の策から生まれた図夢歌舞伎の好評価は、「映像用の歌舞伎ドラマをつくるステップになったような気がする」との思いを深めたようで、そのためにもまずは「今月、来月はどこどこでの公演という歌舞伎スケジュールの中に図夢歌舞伎が入る、存在するようになったらいい」とも。確かに、オンライン配信の歌舞伎は誰もが自分に合わせて自由に見ることができる。日常の中に歌舞伎が入り込むことになろう。だが、だからと言ってともすると心配の声が出る歌舞伎座や国立劇場など劇場に足を運ばなくなるというということにはならないはず。劇場という独特の空間の中で、芝居はもとより一時間半という長い幕間で食事をしたり、土産物を買ったりの非日常感を味わうことができるのがリアルな歌舞伎の魅力といっていいからだ。むしろ、映像歌舞伎を見て興味がわき、劇場に行きたくなるという相乗効果も期待できるかもしれない。まさに、10代目が夢見る映像とリアルの両立である。
400年という伝統芸能だからといって、変えていけないわけではない。それどころか解釈や演技のありようも、目にははっきりわからなくても時代に合わせ、環境変化に合わせて微妙に変わっていくのだと思う。また、変わらなくては次世代に残らないのだとも思う。
400年の歴史のなかで映像化に踏み出したという2020年はまさに歌舞伎史に残るエポックメーキングな年になったといえよう。コロナ禍での窮すれば通じるということか。災い転じて福ということか。
日本記者クラブで会見した松本幸四郎の表情は、映像化の手ごたえ、そして8月から再開された公演のせいもあってか生き生きと明るいものがあった。歌舞伎座での上演再開の日、「コロナ感染防止対策で会話はダメ、掛け声もダメということで、客席は幕が開く前はフリーズしたように静かだったが、幕が上がると同時に割れんばかりの拍手が鳴り響いた。歌舞伎ができる喜びをかみしめた。また、大向こうからの掛け声も禁止ということだったが、花道に近い客席のお客様が私の屋号‘‘高麗屋‘‘と書いた紙を掲げてくれたのを目にしたときは本当に感激した」とのエピソードも披露した。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
一般社団法人工務店フォーラム 災害に強い家づくりセミナー 第3回「いつまでもケガをしづらい家づくり」
2025.06.18
-
【住宅業界関係者向け】フォーリンラブ・ハジメの釣り教室
2025.06.09
-
アキレス・シネジック 熱中症・水害・台風から身を守る防災術
2025.06.09