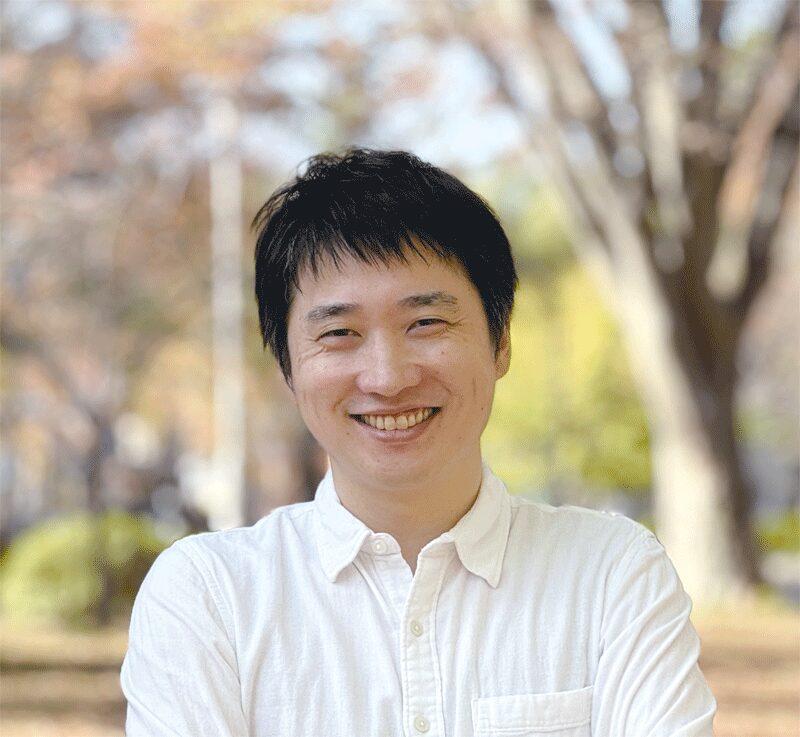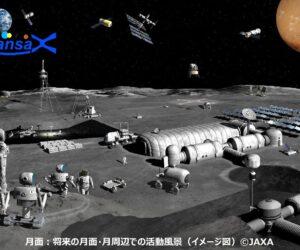玄関まわりの植物がうつ予防に貢献 近隣との交流を促す可能性
千葉大学予防医学センター 吉田紘明 特任助教
千葉大学予防医学センターの吉田紘明特任助教、花里真道准教授、鈴木弘樹准教授らの研究チームが、玄関まわりの植物が高齢者のうつ予防に貢献する可能性があるという研究結果※を発表した。
住まいづくりの中で、近年緑を取り入れた環境は大きく注目を集めている。
玄関先の植物はどのように高齢者のメンタルヘルスに影響を与えるのか。吉田特任助教に話を聞いた。
―高齢者のうつ予防として、玄関まわりに着目されたのはなぜですか?
海外の既往研究で、玄関まわりにポーチ空間(地面から一段高くなっていて、屋根があり、人が座れるスペースがある空間)が多い地域に住んでいる人は身体機能が維持・増進される、社会的支援が受けられるという結果がわかっていました。また、別の研究でも、家の屋内と屋外をつなぐ空間として玄関まわりは着目されており、玄関先や前庭での活動が、道路を行き交う人との気軽な交流を生むのではないかという文献はいくつか目にしていました。そうした交流がメンタルヘルスに良いということは既に分かっていたので、玄関まわりの特徴とうつの関係性について研究することにしました。
―調査を進めるなかで、予想外の気づきや発見はありましたか。
最初は主に戸建住宅での効果を想定していたのですが、住んでいる住宅の種類で分けてみたところ、集合住宅居住者で関連性が見られたのが意外でした。
戸建住宅では、統計学的に有意な関連は見られませんでした。集合住宅の場合、各戸の玄関まわりで植物を育てるには、基本的にプランターや植木鉢で育てることになります。一方で、戸建住宅では、庭への地植えも多いです。その違いが結果に影響を与えたのではと考えています。
プランターや植木鉢は、水やりなど毎日の手入れが必要です。毎日の手入れが身体活動に繋がりますし、毎日玄関前に出る必要があるため人との交流も生まれやすくなります。しかし、地植えは鉢植えに比べて手入れを要しない場合が多いです。そのため、玄関まわりの植物に、地植えが含まれる戸建住宅では、関連性が見られなかったのかもしれません。
今後の調査では、玄関まわりの植物が、社会的交流を促す可能性があるという点に着目したいと考えています。園芸活動によって、身体活動が促されることは知られているのですが、玄関まわりでの園芸活動が社会的交流を促すのかはそれほど明らかになっていません。玄関まわりに植物があることが近所の人との交流を促す、それを通してメンタルヘルスに好影響が出るのかまで分析していきたいです。
―この結果は、高齢者だけでなく他の年齢層でも当てはまると思いますか。
高齢者の場合、働いていないことも多く、その地域で過ごす時間が長いため、居住環境がメンタルヘルスに与える影響は大きいと考えられますが、若い世代ではメカニズムが変わってくると思います。例えば、子育て世代では、子どもが遊べる広い前庭があることが重要かもしれません。子どもが前庭で遊ぶことで、親や近所の人が顔を合わせる機会が増え、自然な交流が生まれることが想像されます。
また、今回は都内在住者への調査でしたが、高齢者が対象であっても、郊外、地方など住んでいる地域による差も大きいと思っています。郊外では、広い敷地に建つ住宅が多く、都市部よりも前庭がしっかり確保できると思います。こうした住宅では、前庭に日射しや雨をしのげる屋根があることで、庭での活動が促され、その結果、メンタルヘルスに良い影響をもたらす可能性があります。
データの取得が難しく調査ができていませんが、フェンスの有無や素材による可視性も影響があるのではないかと考えています。例えば、玄関まわりに植物があり、世話をしていても、可視性の低いフェンスを設置していると、道路を歩いている人との交流は生まれないと思います。
こうした環境の違いによる結果の差も確認していきたいです。
―今回の研究結果を踏まえて、住宅や庭空間をつくるときにどのようなことが重要だと考えますか。
玄関まわりに植木や花があることはいいのですが、道路や共用廊下にまではみ出してしまうと、通行の妨げになってしまいます。そのため、敷地側でしっかりと庭空間、植物を育てられるスペースを設ける必要はあると思います。そうした植物を育てるスペースが道路に面しているとよいのかなと感じました。
住まいと健康については、これまで室内環境に関する研究が多く行われてきましたが、近年は住宅を取り巻く環境にも注目が集まっています。人の健康は住宅の中だけではなく、地域の緑の多さや歩きやすさ、交通騒音といった外の環境にも影響を受けていることが分かっています。そのため、住宅の外も含めた住環境の整備が重要だと考えています。
研究概要
■東京都A区に在住する、65歳以上で要介護認定を受けていない2046人(女性1141人、男性905人、平均年齢約75歳)が対象。
■2022年1月と2023年10月の2時点で自記式質問票にて取得した調査データを使用。
■うつの評価は、2023年時点の「老年期うつ評価尺度(GDS―15)」を用いて、得点が5点以上を「うつあり」、5点未満を「うつなし」とした。
■2023年時点で玄関まわりにある「階段」「ひさしや軒下」「植木や花」「駐車場」「玄関外側のベンチや腰掛け」「引き戸の玄関扉」「玄関内側の土間」の有無について回答を得た。
調査結果
居住住居: 集合住宅1012人、戸建住宅901人、未回答133人
・2023年時点においてうつの者は、458人(22.4%)だった。うち、集合住宅居住者は245人(23.1%)、戸建住宅居住者は194人(21.5%)、住居不明者は19人(22.6%)。
・玄関まわりに植物がある者は、ない者と比べてうつの割合が16%低かった。特に、集合住宅居住者で、植物がある者はうつの割合が28%低く、統計学的に有意な差であった。戸建住宅居住者で、植物がある者はうつの割合が15%低く、統計学的に有意とは言えないものの関連を示す傾向が見られた。
・同研究は、うつと玄関まわりの特徴を同時点で取得している横断研究であるため、因果関係は明らかにできないが、この関連には、
◯社会的交流の増進:植物の手入れ中に近隣住民との挨拶や会話が生まれやすくなり、交流が促進されることで、メンタルヘルスの改善につながった可能性
◯身体活動の増進:植物の世話を通じて身体活動が日常的に行われることで、うつの予防や緩和に寄与した可能性
◯ストレス軽減:自然とのふれあいを通じてストレスが軽減され、メンタルヘルスの改善に役だった可能性
の3つのメカニズムが関与していたと考えられる。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
日本セルロースファイバー断熱施工協会・デコス 高断熱住宅の結露・カビ対策を古川氏が解説
2026.01.22
-
CLUE 「値下げゼロ」で契約取る付加価値提案術
2026.01.15
-
CLUE 外壁塗装向け「ドローン×デジタル集客」セミナー開催
2026.01.15