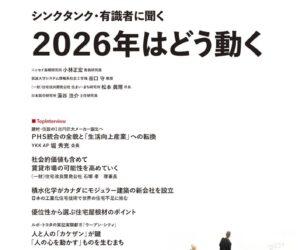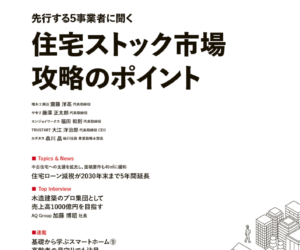楽・守・形のキーワードで選ぶ住宅屋根材
市場のニーズに応える各社の提案
住宅屋根材を取り巻く環境が移り行くなか、各社は市場の変化に対応し、さまざまなテーマへの提案を進める。
今回は「楽」(施工性)、「守」(防災性)、「形」(屋根形状の変化への対応)をキーワードに、各社の取り組みを探る。
2024年の住宅市場は、円安などを背景とした資材の高止まりや労務費の高騰などにより、価格の上昇が続いた。屋根材各社でもこうした影響から価格改定が相次いでいる。また、24年の新設住宅着工数は23年から引き続き、連続でマイナスを記録するなど動きが鈍い。一方で、空き家活用を促す法改正が進む。また、住宅着工の多かった90年代後半~00年代前半頃に建てられた住宅が、改修時期を迎えるなど改修市場は勢いを増している。
一方で、建設業界で大きな問題となっているのが人手不足だ。国交省によると、建設業の技能者就業数は97年の455万人から10年には331万人に、20年には318万人へと減少している。
また、台風の大型化や集中豪雨の頻発など、自然災害が甚大化しているなかで、災害対策も欠かせない。
住宅価格が高騰するなかで、コストを抑えられる狭小住宅の増加や太陽光発電設備の普及により、屋根形状にも変化が現れる。
屋根材を取り巻く市場環境が大きく変わるなか、各社の取り組みが加速する。
施工性・防災性・屋根形状変化への対応という大きく三つの視点から今の屋根材市場を覗き見る。
人材不足+高齢化で
【楽】に施工できるかが大きなポイント
24年4月に建設業の時間外労働の罰則付き上限規制が導入され、一部の工場などの建設に遅れが出るなど人手不足の深刻さが顕在化した。さらに25年以降、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年問題も話題となっている。こうしたなかで、屋根材もどれだけ早く簡単に施工できるかが重要なポイントとなっている。
三州瓦メーカーの鶴弥は、新設住宅着工数が落ち込むなか、瓦の販売も厳しい状況を強いられているという。そうした状況下でも歩留まりの改善や販売量に応じた柔軟な生産体制などにより、24年度は前年比1割増で着地する見込み。特に、古くからある和形のJ形瓦は、生産メーカーが少なくなってきている中で、変わらず生産を続けている数少ないメーカーとして重宝されているという。
同社は、23年より陶板屋根材「スーパートライ美軽」と粘土瓦「F形」にフルプレカットシステムを導入。葺き始めや葺き終わりの斜めになる部分などのカットを事前に自社工場で行う。費用はかかるが廃材削減にもつながるため、省力化や環境貢献に感度の高い住宅メーカーなどに注目してもらえるサービスとみて、提案を行っている。
また、同社は昨年、AIソフトウェアを活用し粘土瓦の外観検査(選別)工程を自動化する装置の導入に向けて取り組みを開始。目視確認による良否判定基準の微妙なばらつきや、ヒューマンエラーによる不適合品流出リスクを抑える。現在、F形瓦を製造する主力工場、阿久比工場(愛知県知多郡)で試験的に導入を開始し、25年中に他の工場にも導入する予定だ。

ケイミューは、20年にスレート系屋根材「カラーベスト」のプレカットを開始している。現在、月500棟以上の物件でプレカット材が採用されており、その採用は徐々に増えてきているという。「屋根工事の施工者が減少し、作業者の年齢も上がる中、将来的な視点からプレカットを選ぶ住宅会社の増加が期待される」(屋根材事業担当 川口剛執行役員)と、人手不足の解決策としてプレカットの注目度は高まっているようだ。
「カラーベスト」は、プレカットにより約20%の工期短縮が見込まれるほか、廃材の削減による環境価値の向上や、屋根上での作業が減ることによる安全性の確保などのメリットがある。同社は、これらのメリットに関心を持つ顧客に対して、具体的な例や数値を用いて提案活動を行っている。
旭ファイバーグラスは、アスファルトシングル屋根が主流のアメリカから長年ラミネートタイプのアスファルトシングル屋根材「リッジウェイ」を輸入販売している。ガラス繊維に耐候性のあるアスファルトを含浸させ、粒状彩色石を添加してプレスしたもので、一枚一枚が別のデザインをしているため、施工した際に屋根の意匠性が高くなる。
衝撃を吸収する特性を持ち、くぎ打ち機で施工できるため、施工の負担も少なく、意匠性と施工性のバランスが良いことから市場に広く受け入れられた。くぎ打ちライン上部を帯状に彩色石から砂に変更することで、パレットに積んだ際に平滑に積むことができ、冬場の波打ち現象が改善できることもポイントだ。カッター切断で様々な寸法に合わせられるため、材料のロスも少ない。
コロナ禍での搬入ストップや円安により、厳しい状況にあるというが、そうした状況下でも「専任の担当者による施工指導や、アフターサービスなどをしっかり行っていることに対しては評価が高い。長年アスファルトシングル材を扱ってきた信頼性を強みに一念発起して戦いたい」(営業本部グラスウール営業支援グループ 池田昌彦グループリーダー)とする。
新築市場へ向けた金属屋根材をメーカーとして提供するのがハウゼコだ。金属屋根はもともと板金加工業者が製造・施工していたため、メーカーとして金属屋根材を販売している会社はまだまだ少ない。ただ、板金加工業者は屋根について詳しくないため、屋根の通気が十分でないこともあるという。そうした課題解決のため、同社が開発した通気機能を一体化した立平葺き金属製屋根材が「デネブエアルーフ」だ。新築住宅に金属製屋根材を施工する場合、透湿抵抗が低い野地合板やアスファルトルーフィングに密着した施工となり、毛細管現象により、軒先、野地合板などに雨水が浸入しやすい。「デネブエアルーフ」は、独自の形状に加工した通気リブと透湿ルーフィングの組み合わせで通気層をつくるため、通常の金属立平屋根と同じ施工で通気を取ることができ、採用数を伸ばしている。

改修市場は施工性の良いカバー工法に広がり
一方で、近年盛り上がりを見せるのが改修市場だ。
屋根のカバー工法では、金属製屋根材が先行するが、本格的なストック時代を迎える中で、様々な素材の屋根材によるカバー工法で改修市場の開拓を目指す動きが目立つ。
アイジー工業の原田康営業第1部長は、「新築市場が厳しくなっている一方で、カバー工法の屋根改修で利益を出す事業者は少なくない。また、大手の住宅メーカーも、OB顧客への改修提案に本腰を入れ始めている」という。
アイジー工業のリフォーム向け金属製屋根材「スーパーガルテクト」は、アルミニウム亜鉛合金めっきのガルバ鋼板にマグネシウムを2%添加した「超高耐久ガルバ」を採用し、高い耐久性を実現した商品。特徴的なのが、表面に特殊なちぢみ塗装を施している点だ。意匠に独自性を持たせることを目的に行ったものだが、施工業者からちぢみ塗装があると急勾配の屋根を施工する際に足が滑りにくいと好評だ。また、長さ6尺品も標準仕様としているため、狭小住宅の屋根でも取り回しをしやすい。リフォームは既に住宅が立ち並んでいるところで作業をするため、住宅同士の間隔が狭い分譲地などで取り回しをしやすく、短くて軽いという特徴は強みになる。


また、金属屋根は、屋根材同士を嵌合してつなぎ合わせていくが、緩すぎると雨漏りの原因となり、きつすぎると施工が大変になるためミリ単位でのバランス調整が必要となる。しかし、アイジー工業は「金属サイディング材を長年扱っていた歴史もあり、金属の成形技術は自信がある」(原田康営業第1部長)というように、嵌合部分についても品質の高さに評判を得ている。
その他、改修用唐草や、カバー工法向けの下地材など専用部材を取りそろえており、改修作業の簡略化、均一施工に寄与する。
ニチハは、金属製屋根材「超高耐久横暖ルーフ」を販売している。高い耐候性を誇るフッ素塗装鋼板で平葺きの「横暖ルーフ プレミアムS」、山高で意匠性の高い「横暖ルーフαプレミアムS」、ポリエステル塗装鋼板で平葺きの「横暖ルーフS」、山高で意匠性の高い「横暖ルーフαS」、短尺の「横暖ルーフS 1820」、南欧風の独自デザイン「横暖ルーフαS窯変」と、6品種19アイテムという幅広いラインアップが強みだ。カラーバリエーションも多い。「塗装が主流だった屋根改修の中で、築20年以上の場合はカバー工法を行う流れが活発化してきた。当社は多彩な商品群で、ニーズに合わせた選択ができる」(金属外装営業部)ため、出荷量は堅調に推移しているという。
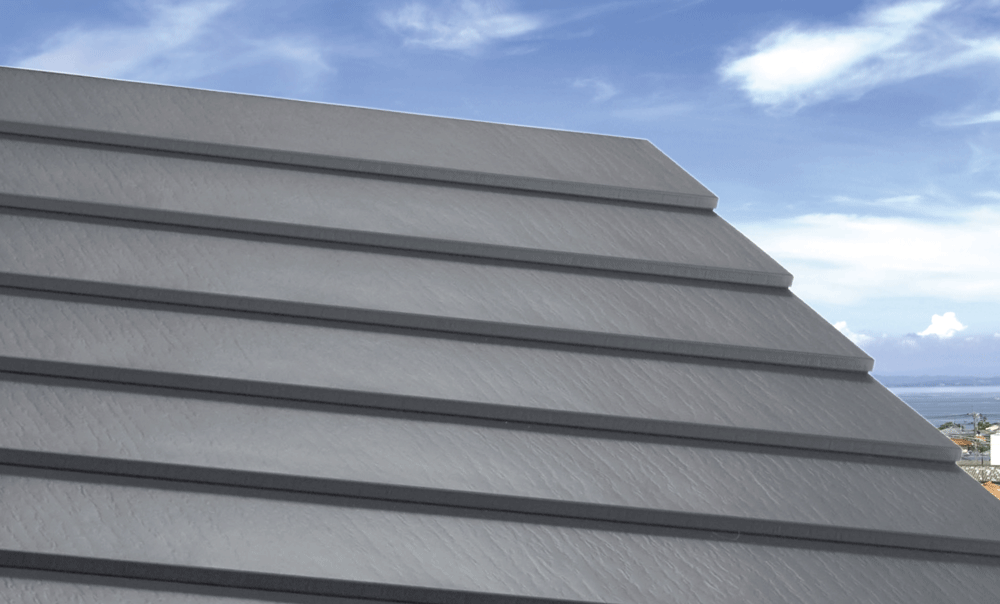
施工性においては、軽量であることを最大の強みとする。20年には、梱包入数を8枚から6枚へ変更し、従来品より屋根上への搬入を行いやすくした。また、同時期に長さの短い6尺品をラインアップし、狭小地での施工性を向上させた。
また、同社は認定工事店制度による職人育成と、施工方法の理解の拡大にも力を入れている。年に数回研修会を開催しているが、住宅メーカーやリフォーム業者の施工業者に対する工事品質への意識が変わってきたことなどを背景に、以前にも増して認定取得への需要の高まりを感じているという。
こうした流れの中で、鶴弥は、改修市場に対して「瓦の提案を行いながらも、要望に合わせて金属屋根製品も提案をできるように拡大」(角森取締役営業本部担当)し、リフォーム需要の取り込みを加速する。複数メーカーの金属製屋根材を揃えており、「瓦メーカーでありながらも鶴弥に相談すれば一通りのものが揃うというイメージに変えていきたい」考え。
新たな屋根改修の選択肢として市場開拓を狙うのは田島ルーフィング。23年2月に改修向けのアスファルトシングル材「OHVAN(オーヴァン)」を発売した。大きな特徴は、1㎡あたり5.5枚で施工できる大判サイズであること。通常のシングル材は1㎡につき7~9枚必要なため、作業スピードが格段に速くなる。182㎜と長い葺き足で、カバー工法をした際に既存屋根の段差ができず、仕上がりもきれいだ。
また、国内の工場であらかじめ接着剤を塗布しておくプレセメント加工によって、現場で接着剤を塗布する手間が省けるため、効率化に繋がる。
さらに、改修用として展開するにあたり、専用のくぎを開発した。通常のくぎをカバー工法に使用すると、既存屋根の硬さに負けて曲がってしまう打ち損じが多く発生する。そのため、改修用には既存の屋根材の上からしっかりと打ち抜ける硬いくぎを販売する。
改修市場はこれから期待される市場であり、競合も多いため急激に販売数を伸ばすことは難しいが、商品案内をした際の反響は良く「着実にリピーターとなる施工業者の方は増えている」(住建営業部 住宅建材課 流通グループ・丸山晋グループリーダー)。

旭ファイバーグラスは、「リッジウェイ」の改修市場での採用拡大を狙う。既存のスレート瓦の上から直接施工する「カバー工法」で訴求を強めたい考え。
ケイミューは現在、改修提案として、金属製屋根材「K︲METAL」によるカバー工法に加えて、瓦屋根材「ROOGA」によるカバー工法を提案している。また、「カラーベスト」を使用したカバー工法の研究開発など、新たな取り組みを進めている。
激甚化する災害から【守】る
防災性は当たり前の時代に
常に屋外の過酷な環境にさらされる屋根材は、防災性も大切なポイントとなる。地震大国の日本では、地震が起きた際にも容易に屋根材が落下しない頑丈さだけでなく、万一屋根が落下、飛散した際の安全性も求められそうだ。また、近年増加しているのが、夏場の集中豪雨だ。地球温暖化での気温上昇などに伴い、十数年前には考えられなかったような自然災害が巻き起こっている。
鶴弥の角森取締役は「基本的に防災性能を有していない製品は受け入れられない。当社は9割以上を内製化しており、すべての商品が防災性能を有しており、鶴弥=防災性の高い瓦屋根と認識されている点が採用への強みとなっている」という。
23年には耐久性を目に見える形でPRするため、粘土瓦の60年製品保証を開始したが、長期保証をうたう住宅会社などからは、エンドユーザーに瓦の耐久性を説明する際に説得力を持たせられると反響は上々だ。
また、同社は陶器瓦の素材、耐久性、高級感はそのままに、陶器瓦から28%の軽量化を実現した陶板屋根材「スーパートライ美軽」もラインアップしている。風速46m/sの強風に耐えられる耐風圧性能や寒冷地にも使用できる耐凍害性を有しており、注目度の高い商品だ。「まだ採用は少ないが、瓦の性能に軽さが加わると大きな武器になることは実感しているので、軽量な商品の開発を進めていきたい」(角森取締役)としている。
旭ファイバーグラスの「リッジウェイ」は、2層構造のアスファルトシングル材であることから、耐久性が高い。軽量なため地震にも強く、再度注目度が高まっているという。また、柔らかい屋根材であることから、割れることがなく、万一飛散しても被害を最小限に抑えられる。
耐風性能は、標準仕様で風速38m/sをクリアしている。接着剤やくぎの本数を増やした強風仕様では風速45m/sまで耐えることができ、沖縄などの台風が多い地域でも採用できる。

ハウゼコの「デネブエアルーフ」は、通気一体型の金属製屋根材で、野地板の腐朽を防止するため、台風などの強風で屋根が飛散することを防ぐ。毛細血管現象で雨水が浸入した場合、軒先唐草のない上部の野地板が腐るため、強風などで飛散する可能性が高まる。
24年4月からは「デネブエアルーフ小屋裏漏水保証」を開始しており、施工業者、工務店を対象に、新築後10年の換気棟からの漏水に対して最大500万円の補償を行う。
自然災害の多発で防災視点からの改修需要も
台風や豪雨被害が全国各地で激甚化・頻発化する中、改修市場においても、防災性の高い屋根への交換が大きなトレンドになっている。交換したいニーズが高まる。
例えば、金属製屋根材は重量が軽いため、地震発生への安心感が高い点が強みだ。アイジー工業の「スーパーガルテクト」は、風速65m/sの耐風試験において、飛散することはなく、風にも強く安心だ。万一大きな災害で屋根に被害が生じる場合でも、ビス留めがしっかりしていれば割れて落下することはほとんどないこともポイントだ。こうした点から「スーパーガルテクト」は災害後の屋根改修などで採用されることが多い。
24年には、ガルテクトシリーズの発明考案に長年従事してきた、菅野良彦 取締役常務執行役員が黄綬褒章を受章している。アスベストの問題などで既存屋根をはがさずに施工できるカバー工法の必要性が高まるなか、簡便な方法で防水性能を確保できる構造を考案し、高い専門技術がなくても金属製屋根材によるカバー工法を施工できるようにしたことで、普及に貢献、災害時の速やかな生活再建にもつながるとして評価された。
改修市場が盛り上がるなか、「スーパーガルテクト」の販売も好調で、24年度は前年比2割強の数量増加を達成する予定だ。今後は塗装改修を行っている会社に第2の提案としてスーパーガルテクトを採用してもらうことを狙う。
ニチハは、金属製屋根材は「鋼板のため強度面でも優れており、軽量で耐震性も高い」(金属外装営業部)ことが主な特長で、基本性能として防災性が高いことが武器であるとする。国土交通省の飛び火性能認定を取得しており、火の粉による建築物の延焼を防ぐための屋根に必要な性能を持つ。
「防災性は屋根の性能として必要不可欠なものであり、金属製屋根材の有する防災性も、商品選定時の判断基準となる付加価値になっているのではないか」(金属外装営業部)。
田島ルーフィングの「OHVAN」は、プレセメント加工で強力な接着剤を塗布しているため、風に強いことが特長。同社は長年「ロアーニⅡ」という新築向けアスファルトシングル材を扱っており、プレセメント加工を行ってきたが、「台風などが発生した際にも、屋根が飛散したという報告はこれまできていない」(丸山リーダー)。また、重量も比較的軽量なため、地震などの災害にも強いという。
ケイミューは、「当社の基本姿勢として、社会課題の解決に貢献する商品開発を重視しており、住まいの安全・安心につながる商品づくりを心掛けている」(川口執行役員)とする。
特に、瓦屋根材の「ROOGA」は、一般的な陶器瓦の約1/2の重量で、地震の揺れに強いのが最大の特徴。また、対角2点で釘止めすることで、風による飛散を防ぐ設計となっている。能登半島地震後、新築・改修の両方で軽量な瓦の需要は高まっているとし、24年度の「ROOGA」の販売は、前年度比で10%以上の成長を達成している。
住宅デザインが変わり
屋根【形】状が変わる
シンプルなデザインでスクエア型の住宅人気の高まりや太陽光発電設備の設置など様々な理由から、屋根形状の変化も顕著に表れている。
(独)住宅金融支援機構が、2024年に公開した、令和5年度(2023年度)の「フラット35仕様実態調査」の結果では、「片流れ」が調査年度ごとにその存在感を大きくしており、前回調査の平成29年度(17年度)から、11%増の41.5%となった。次に多いのが「切妻」の31.5%。「片流れ」と「切妻」の2パターンで、全体の7割以上となっている。一方で、「寄棟」は調査年度ごとに少しずつ割合が減っており、今回の調査では13.2%であった。
ケイミューの川口執行役員は、「住宅トレンドの変化や太陽光発電の普及の影響により、2・5寸以下の緩勾配屋根で片流れや切妻などの屋根形状が増えている」と指摘する。27年度を目標年度とする住宅トップランナー基準の見直しでは、太陽光発電設備の設置義務化が要件に含まれる見通しとなっており、片流れ、緩勾配屋根の採用は今後も増加を続けそうだ。

こうした変化に対し、各社も様々な戦略を練る。
鶴弥は、片流れに多い緩勾配屋根や、太陽光発電設備の設置への対応力向上を図る。例えば、防災洋風瓦のスーパートライ110シリーズの「タイプIPlus」は、条件によっては2寸勾配まで対応できる。また、24年9月から「防災J形瓦エース」をリニューアル発売しており、従来4寸勾配以上での対応だったものを2.5寸勾配までの緩勾配屋根での使用も可能にした。傾斜の緩い緩勾配屋根は、屋根上に水がたまりやすいため、高い防水性能が必要とされる。防水の要である水返しの高さを高く変更することで防水性能を向上し、あわせて専用の役瓦についても防水性能を高めた。
これまで、緩勾配屋根対応のJ形瓦は別商品として展開していたが、「防災J形瓦エース」をリニューアルし1本化したことで、施工業者からは、使いやすくなったうえに、緩勾配屋根以外の屋根で使う際の高い防水性能が得られるので安心感があると好評だ。
田島ルーフィングは、緩勾配対応として、新築向けの「ロアーニⅡ」を下葺材との組み合わせによっては1.5寸勾配までの屋根で防水保証を可能としている。実際に、緩勾配屋根での採用が急増しており、「ロアーニⅡ」の出荷量は微増ながらも、直近の10年間で右肩上がりだとする。
アスファルトシングル材は柔らかく、カッターで切断ができる加工のしやすい屋根材であるため、様々な屋根形状に対応しやすい。複雑な形の屋根でも施工しやすい点は強みと言えるだろう。
ニチハは、22年に片流れ屋根に対応しやすい専用付属部材を発売。「新築への対応はもちろんだが、約15年前から片流れ屋根が流行し始めており、今後改修市場でも片流れ屋根が増加してくると考えている」(金属外装営業部)。また、23年より太陽光パネル設置工法の「PVA︲AT スライド工法」を追加案内し、屋根に掲載できる太陽光パネルメーカーを2社から8社に拡大した。
ケイミューは、住宅トレンドなどの変化に対応する商品開発を進めるとともに、役物を含めた屋根全体のデザイン提案などを進める方針だ。また、住宅トレンドの観点からは、近年「カラーベスト」を壁材として使用する「LAP‐WALL」のニーズが増加しているという。24年には「LAP‐WALL」の下地の施工性を大幅に向上させるEPSボード「KMEW通気パネル」を商品化し、同年のグッドデザイン賞も受賞している。
旭ファイバーグラスは、その軽量さから「リッジウェイ」と太陽光発電設備との相性はいいのではとしている。現在国内で販売されている太陽光発電設備のメーカーにおいてはほとんどのメーカーで対応可能であるとしている。
また、すべての部分が2層になるような施工方法を取り、防水性をしっかり高めることを条件に、2寸勾配までの対応を可能としている。
* * *
新設住宅着工減や資材価格高騰など厳しい環境が続くなか、屋根材メーカー各社は、市場が求める施工性・防災性・形状変化への対応などに独自の提案で答えを出そうとしている。各社の屋根材戦略はますます加速しそうだ。
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
AQ Group・ダイテック 中大規模木造での事業拡大・効率化戦略を解説
2026.02.02
-
リブ・コンサルティング、Cocolive、log build、ダイテック 工務店経営のプロが、勝ち残る工務店の経営スタイルを解説
2026.01.29
-
日本ボレイト、3月5日に第4回JBTA全国大会を開催
2026.01.29